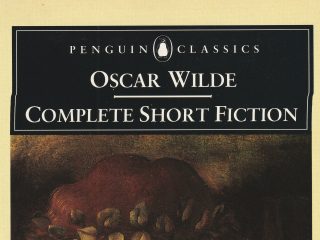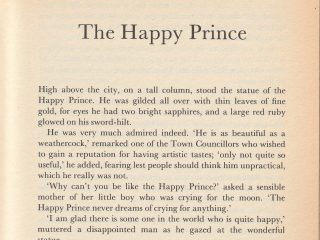「幸福な王子」を読む ➃
「幸福な王子」を読む④
11
やがて、雪が降ってきました。その後に霜が降りました。通りは銀でできたようになり、たいそう光り輝いておりました。
季節は非情なまでの透明な美しさで、いのちを突き刺すような冷たさを送ってきました。出歩く者は誰も彼も毛皮にくるまっているというのに、裸同然になってゆく二人を包むものはありませんでした。
かわいそうな小さなツバメにはどんどん寒くなってきました。でも、ツバメは王子の元を離れようとはしませんでした。心から王子のことを愛していたからです。
働きによって、働きを通して、働きにおいて、一つとなろうとしていたのですが、王子はもう何もかも失って、何をすることも、何を見ることもできなくなったのでした。もはや、つばめが王子にしてあげられることはなく、王子もまたそうでした。つばめは、パン屑をついばみ、自分で自分を暖める以外に何もないのでした。「つばめは王子を心から愛していた」は“he loved him too well”という原文です。それでも王子から離れてゆくには、つばめは王子を愛しすぎていたのです。出来ることは何もなくても、王子を見捨て、王子を離れて行くことなど、できなかったのです。王子のために、また自分のためにも。愛しすぎていたからです。愛しすぎるとは何と悲しいことでしょう。けれど、それはただ悲しいだけではないものです。豊かな悲しさというものもあるのです。
でも、とうとう自分は死ぬのだと、つばめは悟りました。
王子の肩までもう一度飛びあがるだけの力しか残っていませんでした。「さようなら、愛する王子様」ツバメはささやくように言いました。「あなたの手にキスをしてもいいですか」
最後の力を全部使って、つばめは王子の肩に飛び上がりました。いのちの最後の力も王子に近づくことに使ったのです。それはお別れのごあいさつをするためでした。「さようなら、愛する王子様」。それは、いのちがけの愛の告白であり、ささやきでもありました。そして何よりも感謝だったでしょう。「お手にキスさせてくださいませんか?」とは、感謝と尊敬のあいさつです。手の皮膚の金を剥ぐことは、手ではなく金に触れただけでした。だからつばめが王子の手に触れるのは、初めてだったでしょう。最後につばめは王子の手を求めたのです。王子を確かめ、絆を確かめたかったのでしょうか。それでも仕える者の姿勢を崩さないつばめでした。それは、出会ってからの自分のすべてを王子の方に、その手の上に投げ出すことでもあったとも言えるでしょう。
そのとき、王子はつばめの心を知らされると共に、問われるのです。つばめに対する自分の思いを問われるのです。仕事のための道具であることを出なかったのか?最初から最後まで使者に過ぎなかったのか?つばめを育てたとしても、つばめの心そのものには、お前は心を向けなかったのか?「さようなら、愛する王子様」というささやきは、王子の心にも入ったのです。「お手にキスさせてくださいませんか?」と問うつばめを、王子はいじらしいもの、愛すべきものとして自覚したのでしょう。そして、使者でなく、同労者でなくなっても一緒にいてくれた、つばめを見出したのでしょう。
「あなたがとうとうエジプトに行くのは、私もうれしいよ、小さなツバメさん」と王子は言いました。「あなたはここに長居しすぎた。でも、キスはくちびるにしておくれ。私もあなたを愛しているんだ」
それはつばめに感謝して対等の関係に引き上げることでもあったかも知れませんが、たぶんこう言いながら、王子自身もつばめをいかに愛おしい者として愛していたかということを、はっきり知ったのでしょう。ところが勘違いしている王子に、つばめは言いました。
「私はエジプトに行くのではありません。死の家に行くんです。『死』というのは『眠り』の兄弟、ですよね」
私は死を安らかなものと思うことができています。エジプトはもう私の心を惹くものではなくなりました。もうしばらく前からです。今はここがわたしの安らぐ場所なのです。王子に心配させまいとするつばめは、自分が恐れていることを見せまいともし、また死は眠りの兄弟だから恐れるには足りないものだと同意させようとしています。それは、自分が死んだときに、王子が持つであろう罪責感を少しでも軽くしてあげたいためだったでしょう。そして、けれど、それでも本当は怖いのです。それを王子に訊き、そうだよと同意してもらうことで、超えたいと願ってのことでもあったでしょう。
つばめは幸福の王子のくちびるにキスをすると、王子の足元に落ちて死にました。王子の足元。そこがつばめの宿でした。生きるにしても死ぬにしても、どこよりも「さわかな風の通う良い居場所」でした。こうして、つばめはその身の本性が求めるエジプトに行かずに死にました。いのちの愉楽の場所エジプトから、もう一つの別の原理のさらに良き喜びの居場所を見出したからです。エジプトへ帰らなかった物語、あるいはつばめの“出エジプトの記”なのかもしれません。
12
その瞬間、像の中で何かが砕けたような奇妙な音がしました。それは、鉛の心臓がちょうど二つに割れた音なのでした。ひどく寒い日でしたから。
つばめが落ちた瞬間、つばめが王子を選び、献身して働き、すべてを与え尽くして、そして死んだことを、迂闊な王子も、はっきりと知ることになりました。そこにあった、つばめの生の全体と、その稀有にして余りに一途な心を知ったのです。自分が町の苦しむ人々を放っておけなかったように、つばめはこの自分の涙を放っておけない心でいてくれたのだということ、そして、それゆえに、そのためにいのちまで失うに至ったということを知りました。王子は、つばめが自分にとってどれほど尊く愛しいものであったか、自分がつばめを本当はどれほど愛していたかを知ると同時に、そのつばめを自分のせいで死なせてしまったことを知ったのでした。最も愛しく最も大事な存在を、殺した自分の責任、自分の罪を自覚する一瞬には、もうそれだけでも真っ二つに割れてしまうしかない心だったでしょう。
しかし、それはまた、王子にとって、本当に愛された初めての経験だったでしょう。へつらいや上辺だけの、ご機嫌取りでなく、自分を愛し尽くして死んだつばめの存在は圧倒的だったはずです。すべてを与え尽くしたと思っていた王子が、唯一与えなかったものを、王子は知らされたかもしれません。それは自分のいのちでした。それをつばめは王子に与えてくれたのだと、余りに苛烈な罪責感と喪失感と共に、知ったでしょう。貧しい人々を愛し、つばめを愛した王子を、いつのまにかつばめの愛が追い越していたのです。
「その瞬間、像の中で何かが砕けたような奇妙な音がしました。それは、鉛の心臓がちょうど二つに割れた音なのでした。」は、“At that moment a curious crack sounded inside the statue, as if something had broken.”となっています。この「奇妙な」(“curious”)はこの物語の重要なキーワードです。つばめが王子に出会って、最初にお針子の女のところにルビーを運んだあと、「奇妙ですね、今とても暖かい気持ちがするのです」と言ったとき、つばめは“It is curious”と話し始めました。それはつばめが初めて経験したものでした。いわば王子の心がつばめの中に入ってきて暖かく鼓動を始めたことによる「奇妙」さでした。ここも同じです。町を知り社会を知り人間を知ることについては上位にあった王子が、しかし、知らなかったものがあった。それが、いのちがけで愛されるという経験だったのです。
今まで存在しなかった異質のものが入ってくるときに大きな変化は起きます。例えばそれはとても寒い日に、冷え切った牛乳瓶に熱い飲み物が注がれたように、王子の内側につばめの愛が注がれるときに、奇妙な音と共に割れるのでした。「ひどく寒い日でしたから」“It certainly was a dreadfully hard frost”(恐ろしく酷い霜でした)と書かれ、寒さによって割れたとされている比喩的表現の意味もここにあります。王子自身の心が本当は生前の宮殿で、偽りの幸福という霜に覆われていたのかもしれません。
そしてそのゆえに心臓が壊れるという本当の痛みの経験をしたのです。町の人々の悲惨に対する心の痛みとは別の、もっと彼自身のものとしての“heart-break”する痛み。それほどに愛することであり、愛されることであり、罪の痛みであり、喪失であり、悔恨でもあるような痛み。「ずっと向うの」存在への同情、憐みは、「私の町」の悲惨として切実な痛みでもありましたが、高い塔の上からは距離があるものでもありました。他の痛みを憐れむ主体であり、憐む主体でしかなかった王子が、本物の自分の痛みを体験的に知ることであったのです。本当に愛するとは、心裂かれること。心が裂けるのが、愛であるということ。愛は“heart break”であること。“broken lead heart”だけが尊い(“precious”)ものであるということ。どのような言い方が最も良いのでしょう。しかしいずれにしても、解かれ明かされるべき「神秘」すなわち“Mystery”としての“Misery”がここに王子自身としての経験として明らかにされるのでした。
こうして王子は二度死んで、本物の幸福な王子“The Happy Prince”になりました。
13
次の日、市長と市会議員たちは、像を見上げて「おやおや、この幸福の王子は何てみすぼらしいんだ」と言いました。「乞食も同然だ!」とも言いました。そしてもう美しくない王子の像は役に立たないと言って、引き倒し降ろして廃棄処分にしました。彼らは足元に死んでいる鳥も見つけました。王子の像は鋳物工場に回され炉に入れて熔かされましたが、壊れた鉛の心臓(“broken lead heart”)だけが鎔けないので、つばめの死骸の捨てられているゴミの山に投げ捨てられました。
この町の人々が王子およびつばめと対照されることで、上辺だけ見る者たちの真実への無理解さと功利性の裏にある残虐性が批判されています。王子はもはや「幸福」の象徴ではないもの、むしろ逆の「みすぼらしい乞食」のような役に立たないモノ(ゴミ)とされました。しかし、王子が運ばれていった鋳物工場の職工長は、自らの手と目で王子に触れる者として、壊れた鉛の心臓の不滅性を確かに証言する役割を果たしています。それは、決して滅びないものであり、また鎔けてはいけないもの、忘れられてはいけないものを、この割れた心臓が示しているという価値づけでもあるでしょう。
王子の割れた鉛の心臓は、ゴミの山に捨てられて、再びつばめの死骸と一緒になりました。つばめにとってより王子にとって、ここは真の平安の場所であるかもしれません。
最後に登場する天使と神さまも、職工長と同じ価値づけ機能を担う存在です。人には捨てられたものが、神に拾われるのです。
神さまが天使たちの一人に「町の中で最も貴いものを二つ持ってきなさい」とおっしゃいました。その天使は、神さまのところに鉛の心臓と死んだ鳥を持ってきました。神さまは「よく選んできた」とおっしゃいました。「天国の庭園でこの小さな鳥は永遠に歌い、黄金の都でこの幸福の王子は私を賛美するだろう」
かつてこの物語を授業でじっくり考えながら読んでいて、「偉いのは王子とつばめであって、神さまは何もしていないのに、どうして神さまが賛美されなければならないのだろう?」という感想を語った学生がいたことを思い出します。キリスト教が語る「天国」や「栄光を神に帰する」という信仰についての常識がないからだと言ってしまえばそれまでですが、常識は時に何かを見失わせてしまうこともあります。一度立ち止まって、幸福な王子が神をほめたたえ、感謝するとしたら、それはなぜなのか?と問うてみることは良いことだと思います。尊いものとしてゴミの山から拾って天国に入れてくれたからでしょうか?それとも、……?
※写真はワイルドの時代、ヴィクトリア朝のロンドンの街並みの部分。

このブログを書いた人

- 三浦綾子読書会代表/三浦綾子記念文学館特別研究員
-
1962年岡山県生まれ。1992年から2006年3月まで福岡女学院短大および大学で日本の近代文学やキリスト教文学などを講義。2001年より九州各地で三浦綾子読書会を主宰、2011年秋より同代表。
2006年、家族とともに『氷点』の舞台旭川市神楽に移住し、三浦綾子文学館特別研究員となる。2007年、教授の椅子を捨て大学を退職して以来、研究と共に日本中を駆け回りながら三浦綾子の心を伝える講演、読書会活動を行なっている。
著書に『「氷点」解凍』(小学館)、『塩狩峠』の続編小説『雪柳』(私家版)、編著監修に『三浦綾子366のことば』『水野源三精選詩集』(いずれも日本基督教団出版局)がある。NHKラジオ深夜便明日への言葉、テレビライフラインなどに出演。
最新の記事
 おたより2022年10月6日(木)おたより 23 朗読CD「李(すもも)」のご感想
おたより2022年10月6日(木)おたより 23 朗読CD「李(すもも)」のご感想 おたより2022年8月2日(火)おたより 22 「李(すもも)」朗読会のご感想
おたより2022年8月2日(火)おたより 22 「李(すもも)」朗読会のご感想 おたより2022年5月16日(月)おたより21
おたより2022年5月16日(月)おたより21 おたより2022年3月11日(金)おたより ⑳
おたより2022年3月11日(金)おたより ⑳