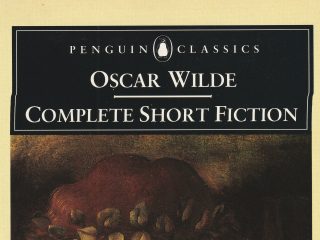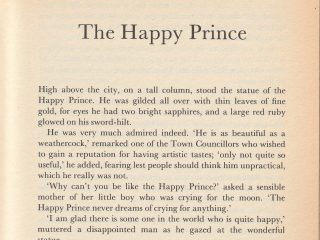「幸福な王子」を読む ②
「幸福な王子」を読む②
5
王子の話を聞いたつばめは思いました。「何だって! この王子は中まで金でできているんじゃないのか。」中まで純金ではない像、表面の金箔をはがせば鉛色になる王子でした。王子の像を作ったのは町の人たちです。現実的で合理的に考えれば、なるほど中まで金である必要はなく、表面を金箔で覆えば事足りるのです。だからこの王子が自分の持っている宝石や金を与えてゆくに従って、鉛の塊になってゆくこと。それもまた大事なプロセスとして描かれるのです。
王子はつばめに言いました。「ずっと向こうの」と。王子には「ずっと向こうの」お針子の女の生活がつぶさに見えるのでした。その貧しさと労苦も手の傷と荒れも、トケイソウ(passion flower=受難の花)の刺繍という仕事の詳細も、その傍に臥す病気の息子が泣きながら「オレンジが食べたい」と訴えていることも。王子はつばめに「ずっと向こう」を指さし、共に見ようと招く者でした。人は「ずっと向こうの」存在など見えもしないし見ようとも思わないものです。すぐ近くや知り合いの間で起きた事件ならば関心を持ち、心痛めることもありますが、「ずっと向こうの」世界に心を向ける人は稀です。つばめは言います。「私はエジプトへ行きたいんです」と。エジプトはもっと遠い場所です。けれど、それはつばめにとっては実際の距離は遠くても「ずっと向こうの」世界ではありません。自分が享受すべき、仲間が先に行って待っている快楽の世界あり、つばめの最大関心事でした。人はそれを詳細にきらびやかに目を輝かせて語るのです。けれど、王子は再び語りかけます。「つばめさん、つばめさん、小さなつばめさん。もう一晩泊まって、私のお使いをしてくれないか。あの子はとても喉が乾いていて、お母さんはとても悲しんでいるのだ」と。名を呼ぶこと、何度もその名を呼んで目を覚まさせ、振り向かせることが大事です。けれど気乗りしない人は、その恩恵を受ける相手がいかに乱暴で失礼で面倒な存在であるかあら探しし、そうしてやるにいかに相応しくない存在であるか述べ立て、言い訳をします。こんなとき人は見事に饒舌です。そしてその話の中に自慢話まで上手に混ぜながら話すものです。つばめは王子に、男の子は粗暴だが、彼らが投げる石なんか簡単によける俊敏さを自分は持っているのだと言いました。
でも、幸福な王子がとても悲しそうな顔をしましたので、小さいつばめもすまない気持ちになりました。
王子の “sad” な顔を見たとき“sorry”になったのです。別の訳では「気の毒になった」と訳されています。既に王子の涙に浸されて出会ったつばめは、王子の悲しそうな顔には勝てないのでした。王子の悲しみの内実に同感したのではなく、王子の顔に負けただけなのです。だから「ここはとても寒い。でも、一晩泊まってあなたのお使いをいたしましょう」とつばめは言いました。ちょっぴり恩着せがましく。でも、最初はそんなものなのです。その仕事の目的を意味や価値としては理解しなくても、お母さんに頼まれるから子どもはお使いに行くのです。
6
つばめは、王子に言われたとおり剣のつかのルビーをつつき出して口ばしにくわえ、飛び立ちました。こうして従うこと、お使いをすることが始まりました。いやいやなのです。でも、エジプトへ向かって飛ぶのとは全く違う原理による行動が既に始まったのです。
つばめは宮殿の上を飛んでゆきました。バルコニーの恋人たちは星の美しさに酔いながら愛を語っているのですが、その女が「舞踏会のドレスにトケイソウの刺繍を注文しているのだけれど、お針子なんてみんな怠け者だから心配だ」と言っているのが聞こえました。見栄と虚飾に生きている者たちは王子が見ている「ずっと向こう」の現実を見ることができないこと、むしろ虐げてさえいることも、つばめは分かったでしょうか。つばめは王子に言われた貧しいお針子の家に着きました。熱に浮かされて転げまわる子どもと、疲れ果てて眠り込んでいる母親がいました。つばめは王子のルビーを置き、翼で男の子の額をあおいでやりました。男の子は「ああ涼しい」といって心地よい眠りにつきました。
つばめは王子の元に帰って自分がしたことを報告しました。そして言いました。ここの訳は新潮文庫の方が良いように思います。
「奇妙ですね、いまとても暖かい気持ちがするのですよ、気候はひどく寒いのに」
語りながら、つばめは、初めて経験する自分の中の変化を感じていました。もう少し正確にはたぶん、違和感を覚えるような、ある奇妙な何かが、さっきまではなかったのに、今は自分の中にあるとつばめは発見したのです。王子は言いました。「それはおまえが、いいことをしたからだよ」と。そしてつばめはそのことを考え始めましたが、眠くなってしまいました。疲れたときは考えるより睡眠学習!です。でも、ここで大事なことは、まず一つは、使いをした者はその主人に報告をするべきだということです。業務報告だからというだけではありません。育ててくれるためにお使いに出してくれたお母さんや先生や主人に報告することで、それは本当に意味を持ち、使わされた人自身のものになり、確かな成長になるのです。愛のある指導者はその報告を暖かくかつ的確に理解して答え(アドバイスし)ます。王子は、それは「おまえが、いいことをしたからだよ」と言い、つばめはそれを聞きました。褒められること、肯定的に価値づけられること、教育実践的にはそこが肝要でしょう。
しかし、もう一つ大事なことがあります。ここで言われた「いいこと」は原文では“good action”です。精確には「良い行動」です。では、つばめがした「良い行動」とは何を指しているでしょうか?
王子とつばめの関係は、首謀者と使い走りでした。良いことでも悪いことでも、首謀者にはより大きな責任と罪とあるいは褒められるべき功績があり、手下は手下に過ぎません。何も理解せず、何も共感せず、何も自分では考えずに、言われたとおり実行するのを「ガキの使い」と言いますが、その場合は罪も功も軽いのです。それでも親がはじめてのお使いをした子どもに言うように、良いことを一緒にやってくれたねとまずは褒めているのでしょうか?勿論そうです。しかしよく見ると、つばめは王子に命じられなかったことをしていることが分かります。ルビーを運んだことは、つばめ自身には属さない王子に言われてしたに過ぎないことです。けれど、まずその使いの前提としてエジプトに行くのを延ばしたことはつばめが選んで決定したことです。これはルビーを運ぶことよりはつばめ自身の割合が大きいことです。でもそれも王子に頼まれてしたことであることには変わりありません。けれど、お針子の家で熱に苦しむ男の子の額を翼であおいでやったことは、王子に言われたことではありませんでした。王子の命令の中に、それは入っていなかったのです。
つばめはそのとき、「ガキの使い」ではなくなっていました。自立して、見て、判断して、行動する者になっていました。不思議です。なぜそんなことをしたのでしょう?なぜそんなことができたのでしょう?たぶん、つばめにも分からないのです。大嫌いだったはずの〈男の子〉という人種に親切にしていた自分、それこそ奇妙なことでした。
つばめの行為は倫理的判断や社会問題に取り組む使命による判断などからではなく、王子との人格的関係から始まったものでした。王子の“sad”。つばめにはそれしかなかったのです。そこから始まる使命に従って行為しながら、王子の“sad”を分け与えられ分け持ち始めていたことが、あとから証されているとも言えるでしょう。気がつけば王子の気持ちで行動していたというのが本当でしょう。だから、この奇妙な暖かさとは王子から来たものであり(だから違和感さえ覚える初ものなのです)、王子の心を心として行動したつばめ自身に出現したものでもあったのです。
「良い行動をした者」と名指されて、つばめは考え始めました。初めてする自発的な思索でもあったでしょう。つばめの中で混乱が始まります。エジプトにある暖かさと、「良い行動」によってこの心の中に決して心地悪くはないものとして出てきた奇妙な暖かさ。それは今後つばめの中の最大の葛藤とならずにはいないでしょう。王子の心を理解し始めてしまったことの、不思議な心地よさと不安もつばめを浸していったでしょう。そして眠りに落ちたつばめの中で、この日の行動と心の経験は、その頭にだけではなく、心身全体に内化され肉化されてゆくのでしょう。
7
王子に惹かれ、また王子の使いを果たす度につばめの中ではその反作用のように、エジプトへの思いも強くなっていきました。もうすぐ出発しますと言うつばめに王子は呼びかけて、もう一晩泊まって使いをしてくれないかと頼みました。
「ずっと向こう、町の反対側にある屋根裏部屋」で寒さと空腹のために気を失いそうになりながら戯曲を書いている青年に、宝石を届けて欲しいと言うのです。「髪は茶色で細かく縮れ、唇はザクロのように赤く、大きくて夢見るような目をしている」と書かれているこの青年はオスカー・ワイルド自身のようにも感じます。
「ほんとうは良い心を持っているつばめ」は「もう一晩、あなたのところに泊まりましょう」と言い、もう一つルビーを持っていきましょうか?と問いました。けれど、もうルビーはありません。王子は目のサファイアを抜き取って持ってゆくように言いました。つばめは、「王子さま、私にはそんなことはできません」と言って泣き出しました。
エジプトへの出発を決めていたのに、王子に言われるとすぐに素直につばめは従うことにしました。王子の心に感応してしまう「良い心」を既に内に持っているからです。そして王子の目を抜き取らねばならないことに、衝撃を受けました。「なんだ、中は純金じゃないのか」と心に呟いていたときのつばめは、像として王子を見ていましたが、目のサファイアをつつき出すことを命じられて泣き出したときには、それは宝石という物体でなく、王子の目という尊くかけがえのないものだったのです。王子自身以上に、それはつばめにとって〈痛い〉ことでした。目さえも与えずにいられない王子の“sad”に不可避的に捕らえられてゆく自覚のゆえに震えつつ、それをつつき出さねばならない自分の使命に怯えるつばめは、泣き出しました。こうしてつばめは泣く者になりました。涙に濡れる王子に出逢い、惹かれ、導かれ、感化され、成長し、ここまで来たのです。
「つばめさん、私が命じたとおりにしておくれ」という言葉に、抵抗せずに従うとき、つばめにはつばめの“sad”がもう始まっていると読んでもよいでしょう。その人の心に従わないということはできないのです。その人の心はそれほどに純粋で尊く愛おしいのです。だからこそ悲しいのです。
戯曲を書く青年にサファイアを届け青年の幸福そうな様子を見た後、今度は、つばめはすぐに王子の元に帰って報告するということをしませんでした。それもこの“sad”のゆえです。港に行って、「私はエジプトに行くんだ!」と叫ばずにいられなかったのです。それはつばめの中で起きていることへのつばめ自身の抵抗でもあったでしょう。すべてを与えようとしている王子、その目をつつき出すことで、その自分の心の痛みを通して王子の痛みをも感じてしまうつばめが、そのゆえに、いよいよ王子に惹かれ王子を尊いものとして心から愛し始めてしまう自分に、危機感を感じてもいるのです。目さえ与える王子を愛してしまう自分はエジプトを諦めることになるかもしれないという予感が、既につばめにはあったかもしれません。そして、次には必ず、二つ目の目をもつつき出させようとする王子と、王子と一緒にいるならそうしなければならなくなる自分であることも、つばめは恐れたのです。だから「私はエジプトに行くんだ!」と宣言しなければならなかったのです。
献身とは、そういう恐るべき過程を通るものなのだろうと思います。(つづく)

このブログを書いた人

- 三浦綾子読書会代表/三浦綾子記念文学館特別研究員
-
1962年岡山県生まれ。1992年から2006年3月まで福岡女学院短大および大学で日本の近代文学やキリスト教文学などを講義。2001年より九州各地で三浦綾子読書会を主宰、2011年秋より同代表。
2006年、家族とともに『氷点』の舞台旭川市神楽に移住し、三浦綾子文学館特別研究員となる。2007年、教授の椅子を捨て大学を退職して以来、研究と共に日本中を駆け回りながら三浦綾子の心を伝える講演、読書会活動を行なっている。
著書に『「氷点」解凍』(小学館)、『塩狩峠』の続編小説『雪柳』(私家版)、編著監修に『三浦綾子366のことば』『水野源三精選詩集』(いずれも日本基督教団出版局)がある。NHKラジオ深夜便明日への言葉、テレビライフラインなどに出演。
最新の記事
 おたより2022年10月6日(木)おたより 23 朗読CD「李(すもも)」のご感想
おたより2022年10月6日(木)おたより 23 朗読CD「李(すもも)」のご感想 おたより2022年8月2日(火)おたより 22 「李(すもも)」朗読会のご感想
おたより2022年8月2日(火)おたより 22 「李(すもも)」朗読会のご感想 おたより2022年5月16日(月)おたより21
おたより2022年5月16日(月)おたより21 おたより2022年3月11日(金)おたより ⑳
おたより2022年3月11日(金)おたより ⑳