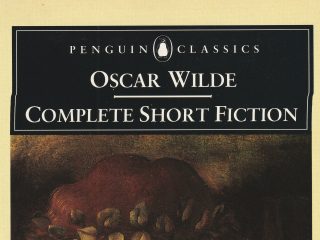「幸福な王子」を読む ③
「幸福な王子」を読む③
8
つばめは言いました。
「おいとまごいにやってきました」
王子は言いました。
「つばめさん、つばめさん、小さなつばめさん。もう一晩泊まってくれないか」
つばめは今度は、すぐには従いませんでした。「もうすぐ冬です。冷たい雪がまもなくここにも降るでしょう」、そして、エジプトの様子を語ってから、こう言うのです。
「私は行かなければなりませんが、あなたのことは決して忘れません。来年の春あなたが与えてしまった二つの宝石の代わりに、美しい宝石を二つ持って帰ってきます。ルビーは赤いバラよりも赤く、サファイアは大海のように青いものにしましょう」
つばめはこうして一時的な別れを提案したのです。王子のためにも自分のためにも。つばめは引くわけにはいかないのです。自分の命とその人が視覚を失うこととが懸かっているのです。でも、語りながらつばめは、それがはじめから負け戦にしかならないことを知っていたのかもしれません。案の定、王子は言いました。
「下のほうに広場がある。そこに小さなマッチ売りの少女がいる」
と。
つばめには分かっていたのです。「行かなければなりませんが、あなたのことは決して忘れません」などと、結論先出しでその人に告げることが裏切りだということも。「宝石を二つ持って帰ってきます」と言うことが、その裏切りを誤魔化し上塗りすることであることも。何もかも与え尽くそうとする王子と、エジプトを片手で握ったまま手放そうとしない自分。貧しい人々に与えて失った分だけ宝石を補完すれば、また与えることができるではないですかと言うことが、合理的に見えて全く的外れな卑怯な言い分であるということも。
その人を、美しかった元の姿に戻して差し上げたいと願う思い、その人に必要なものをお捧げしたいという思い、どれもつばめにとって嘘ではないのです。でも、その人は元の姿に戻りたいとは思っていないし、その人が一番必要としているのは宝石ではなく、この私自身であり、この私が一緒にいてその人の目を抉り出し、やがては皮膚を剥がし尽くしてゆくことが求められるのだということも、ほぼ分かっているのです。二人がしてきたことは合理的な慈善(福祉)事業の法人経営ではありません。この町に悲しみがあり、それゆえに胸が“sad”である限り、止まることのない、目くらむような、それは道なのです。それを分かっていて、「行かなければなりませんが、あなたのことは決して忘れません」と言ったのです。
その言葉が耳に入らなかったかのように、王子は言いました。「下の広場に」と。今度は、王子だけが見えていた「ずっと向こう」の存在ではありません。王子が意図していたとまでは言えないかと思いますが、それはつばめがつばめ自身の目で見るためです。すぐ下のあの少女が見えないのか?と言われているかのように、つばめは胸を突かれたに違いありません。遠くでなく、すぐ目の前の悲惨に目を閉じることなどできないのだと、王子は言っているかのようです。王子は計算して春を待つことを知らないのです。王子にはもうこの冬、いいえこの寒い夜しかないのです。今日途方にくれている、今夜怯え凍えている、今泣いている、その存在しか心にないのです。
マッチ売りの少女はお金を持って帰らなければ父親にぶたれそうでした。彼女は靴も靴下もなく頭にも何もかぶらず、マッチを溝に落としてしまって泣いていたのです。彼女のことが語られたとき、つばめは抵抗できなくなってしまいます。王子の弟子であり、王子と共に働いた者であり、王子を愛した者であるつばめには、もう抵抗の術はありませんでした。
「もう一晩、あなたのところに泊まりましょう。でも、あなたの目を取り出すなんてできません。そんなことをしたら、あなたは何も見えなくなってしまいます」
でも、王子は言います。「私が命じるとおりにしておくれ」と。
つばめは従うしかないのです。つばめは飛び降りてサファイアを少女の手の中に滑り込ませました。少女は「とってもきれいなガラス玉だこと」と言って、笑いながら走って家に帰りました。
戯曲を書く青年はサファイアを発見して「熱烈なファンからのものだ」と思いました。マッチ売りの少女は「ガラス玉」だと思いました。いずれも誤解があります。でも、いいのです。青年は励まされ、彼女は家に帰れたのです。前のお針子と戯曲家は宝石を換金したに違いありません。貧しさが何よりの問題でしたから。でも、この三番目の少女はサファイアを「とってもきれいなガラス玉だ」と思いました。彼女は換金しないでしょう。きれいなものを手に入れたので、それを持って帰ればぶたれずに済むという計算すらないかもしれません。むしろこの「きれいなガラス玉」によって、恐れすら吹き飛んで笑いながら家に帰れたのでしょう。宝石はなぜ尊いのでしょうか?高額な貨幣と換金されるからでしょうか?宝石の本来の価値はその美しさにあります。だから、この少女はサファイアの価値が分からなかったように見えて、お金よりもっと良いものとしての〈宝の石〉としての宝石を与えられ、純粋に受け取ったのです。少女は父親にこの「ガラス玉」を見せて取り上げられ換金され、或いはやっぱりぶたれたかもしれません。でも、もしかすると「ガラス玉」に過ぎないものですから自分の大切な秘密の宝物として隠し持っていくことにするかもしれません。いずれにしても、彼女にはそれは絶望の底で途方にくれて泣いていたときに与えられた、この上なく「きれいな」もの、慰めと希望なのです。だから、彼女こそ、王子の心をもっとも純粋に受け取っているのだとも言えるでしょう。
9
帰ってきたつばめは王子に言いました。
「あなたはもう何も見えなくなりました。だから、ずっとあなたと一緒にいることにします」
王子は言いました。
「いや、ちいさなつばめさん。あなたはエジプトへ行かなくちゃいけない」
ここの王子には形容詞がついていて“the poor Prince”と書かれています。「かわいそうな王子」「哀れな王子」と手元の二種類の日本語訳はなっていますが、もっと端的に「貧しく、みすぼらしくなった王子」というニュアンスも読むべきかと思います。“the happy Prince”と対極であるようで、真の“the happy Prince”に至るための一つの段階なのでした。
「わたしはずっとあなたと一緒にいます」
とつばめは言って、王子の足元に眠りました。つばめにはもう迷いがなくなりました。納得のある居場所、眠れる場所がそこにあったからです。
次の日一日、つばめは王子の肩にとまって、多くの土地で見た沢山の珍しい話をしましたが、王子は、あなたは驚くべきことを聞かせてくれたが、「苦しみを受けている人々の話ほど驚くべきことはない。度しがたい悲しみ以上に解きがたい謎はないのだ」 と言います。ここの英語原文は“but more marvellous than anything is suffering of men and of women. There is no Mystery so great as Misery”となっています。前半には「男と女の悲しみこそ、何ものにもましてふしぎなものだ」という訳があり、後半には「悲惨にまさる神秘はない」という訳もありますが、前半については上の訳、後半は下の訳が良いように思います。ここは男女問題の文脈ではないですし、「謎」よりも「神秘」の方が王子の文脈では正しいように思えます。「謎」も「神秘」も明かされるべき不思議ですが、人間の悲惨や苦難というものは、「謎」のように基本的に知的に解かれるべきものではないでしょう。王子はこの高いところから町の悲惨を見てそれを放っておけないほどに心動かされてしまう心の苦しみの不思議を感じていて、それがこの王子の行動と物語の源なのです。そして、おそらくそれは最後に王子の心臓が割れるに至ってはじめて、その痛みの中で明らかにされる隠された深部でもあるはずですから、そのような展開や奥行きを思うと「神秘」の方が相応しいかと思います。
王子はつばめに「町へ行って見たものをわたしに教えておくれ」と言いました。つばめは、今までは王子の足として、手として働きましたが、目が見えなくなった王子のために、これからは王子の目にもなるのでした。目になることは、まさに「私の町の悲惨が見えてしまう」という王子の〈受難〉に一致してゆくということでもあります。そのようにして、王子と一つになってゆくことは、王子の生き方と一つになるべく献身することであり、エジプトを断念することでもありました。「わたしはずっとあなたと一緒にいます」というつばめの言葉の深いトーン、わずかな悲しみと静かな澄んだ決意とを含む落ちついた音調が素敵です。
10
その大きな町の上を飛びまわり、金持ちが美しい家で幸せに暮らす一方で、乞食がその家の門の前に座っているのを見ました。暗い路地に入っていき、ものうげに黒い道を眺めている空腹な子供たちの青白い顔を見ました。橋の通りの下で小さな少年が二人、互いに抱き合って横になり、暖め合っていました。「お腹がすいたよう」と二人は口にしていましたが「ここでは横になっていてはいかん」と夜警が叫び、二人は雨の中へとさまよい出ました。
つばめは、王子のところへ戻って、見てきたことを話しました。それは、最下層の人々、その日食べるものも宿る場所もないような人々でした。王子は言いました。
「私の体は純金で覆われている。それを一枚一枚はがして、貧しい人にあげなさい。生きている人は、金があれば幸福になれるといつも考えているのだ」
と。
「生きている人」とは、かつて生きていた頃の王子とかれを囲っていた価値観でもあるでしょう。飲み食いから始まる快楽です。王子の言葉には悔恨と諦念の混じった、しかし深い憐みと慈愛のようなものが感じられます。金しか求めていないとしても、それでも、王子は与えるのだと決心しています。
つばめは王子の皮膚である純金を一枚一枚はがして貧しい人々に運び、幸福の王子は完全に輝きを失って、灰色になってしまいました。つばめが純金を運ぶとと、子供たちの顔は赤みを取り戻し、「パンが食べられるんだ!」と大声で言いました。
お針子や戯曲を書く青年には何かを作り出す仕事がありました。王子はその活動の基盤を支えて励ますものを与えたのでした。マッチ売りの少女には家に帰れる希望を与えたのでした。けれど、ここにあるのは人間のぎりぎりの餓えばかりです。状況と効果を考慮して、役に立つから与えるのではありません。効果の少ない、一時しのぎでしかない施しです。換金されて、食料に換えられて、食べられて、なくなって終わりになる、事業としては非常に下手な効果の期待できないものでした。計画も戦略も成果という見返りもないのです。
それは、目の前のいのちの苦しみしか見ていない施しです。でもだからこそ純粋なのです。無駄になってしまう愛です。でも、無駄であることの純粋ということもあるのです。愛とは自分の大事なものを、その相手の必要のために無駄にすることかもしれません。愛には理由がない。愛には耐えがたい痛みがあるだけなのです。そうして、つばめ自身も痛みながら一枚また一枚と王子の金の皮膚を剥ぎ取りました。甲斐のないもののために尊いものが消尽されてゆく。つばめ自身がそれを敢行していったのです。
王子は一枚また一枚とすべてを失い、灰色になっていきました。王子のからだの輝きも、つばめのいのちも貧しくなって尽きてゆきました。その人のそばに生きて、その人のためにいのちを使って死ねば、それでいいのだと、つばめは決めていたのでしょう。その人から独立した別の心を持たないように、手であり足であり、翼であり、目であるようにすること。それが献身です。でも、その人を愛する心だけは、その人とは別の私の心なのです。(つづく)
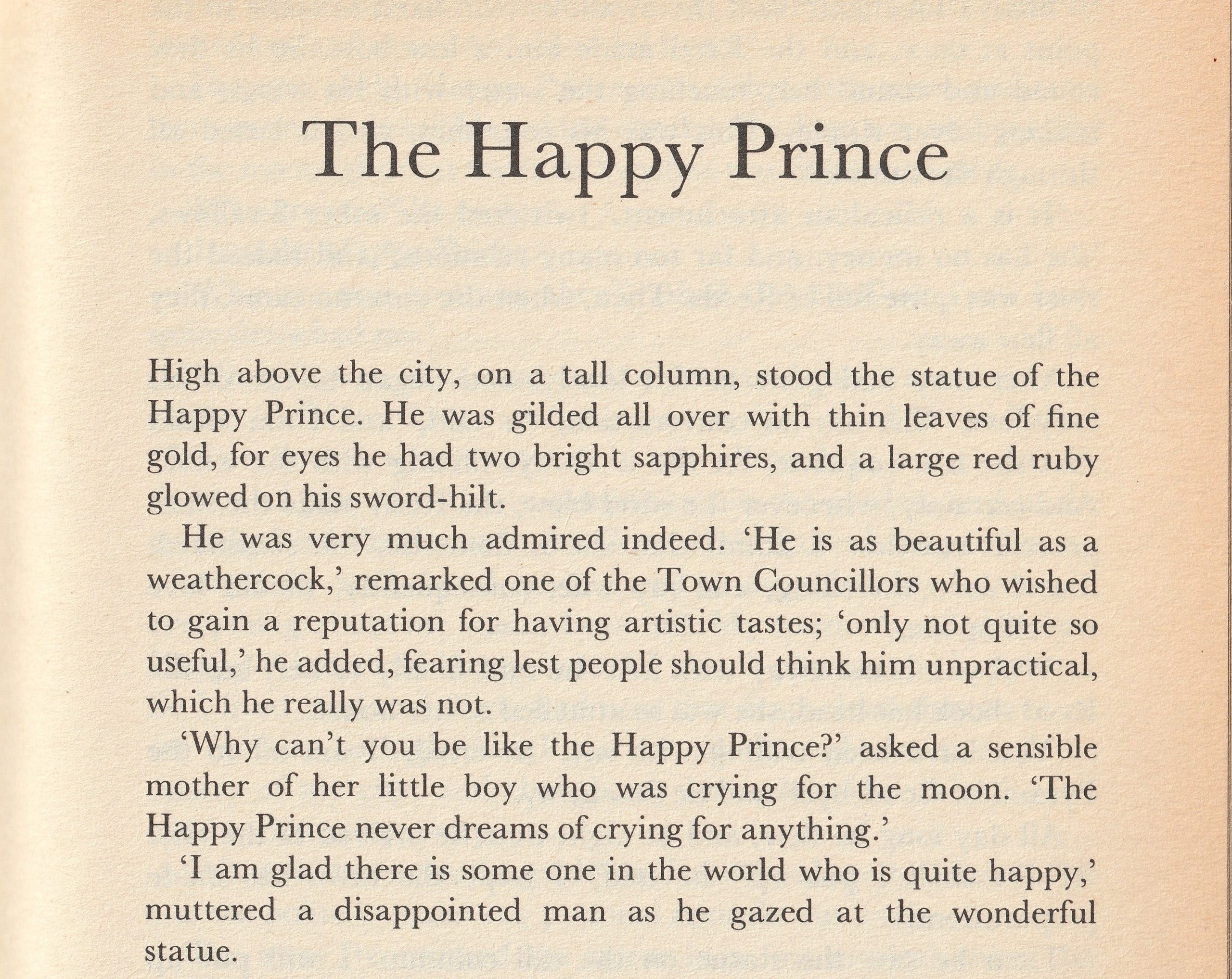
このブログを書いた人

- 三浦綾子読書会代表/三浦綾子記念文学館特別研究員
-
1962年岡山県生まれ。1992年から2006年3月まで福岡女学院短大および大学で日本の近代文学やキリスト教文学などを講義。2001年より九州各地で三浦綾子読書会を主宰、2011年秋より同代表。
2006年、家族とともに『氷点』の舞台旭川市神楽に移住し、三浦綾子文学館特別研究員となる。2007年、教授の椅子を捨て大学を退職して以来、研究と共に日本中を駆け回りながら三浦綾子の心を伝える講演、読書会活動を行なっている。
著書に『「氷点」解凍』(小学館)、『塩狩峠』の続編小説『雪柳』(私家版)、編著監修に『三浦綾子366のことば』『水野源三精選詩集』(いずれも日本基督教団出版局)がある。NHKラジオ深夜便明日への言葉、テレビライフラインなどに出演。
最新の記事
 おたより2022年10月6日(木)おたより 23 朗読CD「李(すもも)」のご感想
おたより2022年10月6日(木)おたより 23 朗読CD「李(すもも)」のご感想 おたより2022年8月2日(火)おたより 22 「李(すもも)」朗読会のご感想
おたより2022年8月2日(火)おたより 22 「李(すもも)」朗読会のご感想 おたより2022年5月16日(月)おたより21
おたより2022年5月16日(月)おたより21 おたより2022年3月11日(金)おたより ⑳
おたより2022年3月11日(金)おたより ⑳