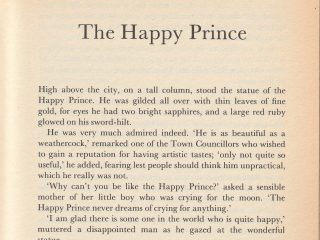「幸福な王子」を読む ①
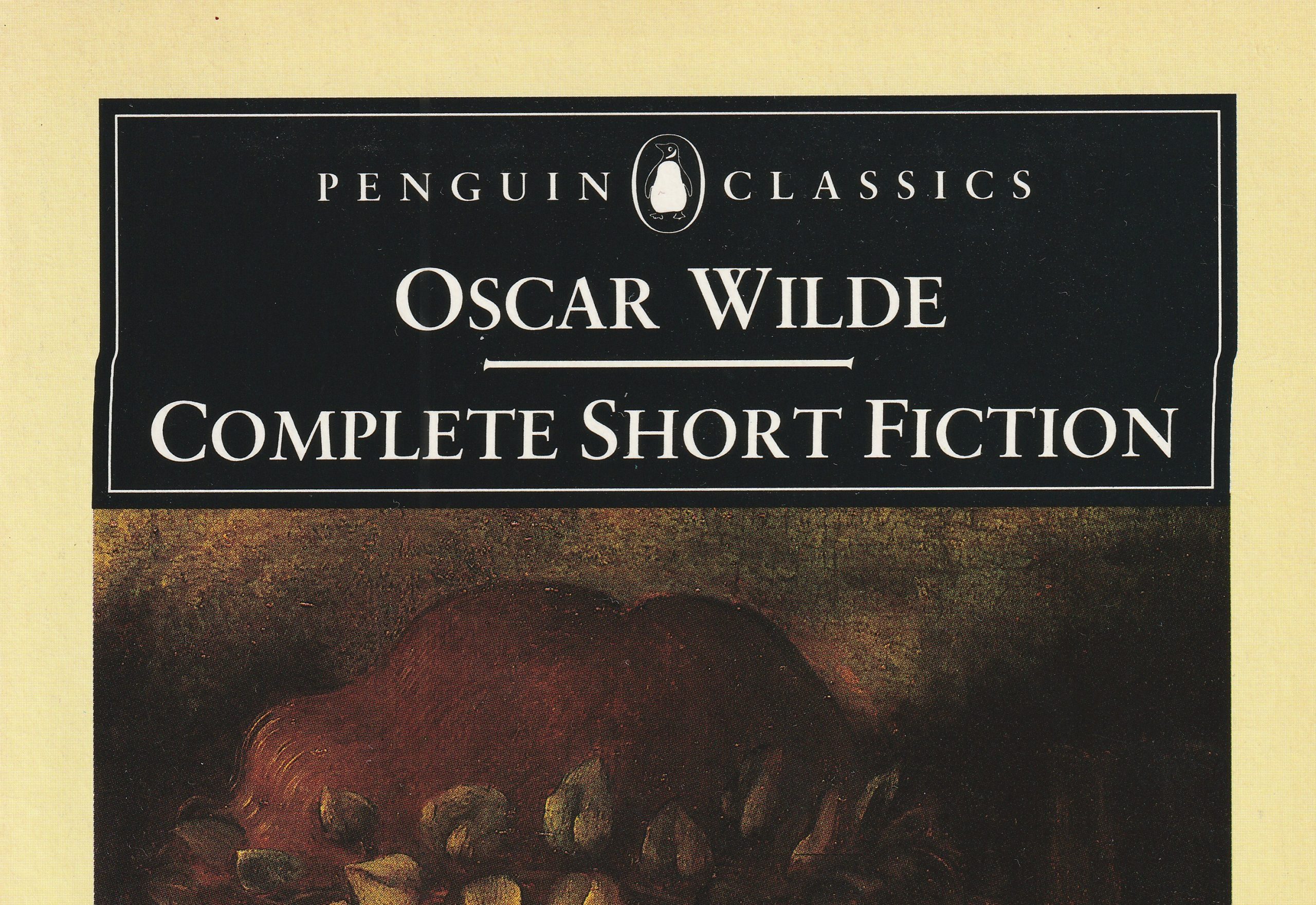
「幸福な王子」を読む ①
0
ワイルドの文学全般に見られる美学ですが、物語の一つの筋は、葦に対する愛に挫折したつばめが王子(像)に出会い成長するというものです。そこには自然的なものから人工的なものへというテーゼがあります。そしてこの王子の像がつばめという自然的なものに愛を教えてゆく過程として物語を把握することができます。このような自然性と人工性のテーマは『ドリアン・グレイの肖像』などと類似、通脈していますし、既にそのように指摘されています。人工性は芸術至上主義的傾向を持つ世紀末象徴主義の一つの傾向で、芥川龍之介なども中期まではそのような傾向を持っていますが、この「幸福な王子」の場合は、これから見てゆくように、人工的な造形芸術であるはずの王子の像が最後には自然的存在であるつばめに追い越され、決定的変容を与えられることになりますから、単純な人工性の優位とばかり読むことはできません。また、この物語をつぶさに見るとユダヤ人への偏見と思われる表現(時代的なものか作者固有のものかは、にわかには分かりませんが)を見ることも出来ます。
1
「幸福な王子」(The Happy Prince)と名づけられた王子の像の物語ですが、では名前につけられた「幸福」とは何だったのでしょうか?彼は幸福だったのでしょうか?彼の幸福はどのようなものから始まって、どのように変化して、どのようなところまで行ったのでしょうか?それらを探るのが、主題であると言ってもよいでしょう。
幸福な王子は、まず外側から語られ始めます。まずそれは像全体を覆っている純金、両目のサファイア、刀の柄のルビーの美しさです。そこから、この像についての町の人々の見方と評価が語られてゆきます。しかしそれは王子を語っているようで、同時に諸刃の剣のように町の人たち自身、すなわち人間というものの価値観や見方を照らしたり切り分けたりすることにもなっています。
市会議員、月が欲しいと言って泣く子どもと、その子を諭す母親、絶望した男、養育院の子どもたち、数学の先生。この人々の内、社会的な地位と権威を持った〈大人たち〉においては、見栄と虚飾と功利主義、現実主義、合理主義、戒律主義が見えてきますが、社会的に弱い立場にある人たちは、曇りない目でそれぞれの角度から幸福な王子の本質を見ているように書かれています。その人々は夢として、慰めとして王子を見、或いは「何かを欲しがって泣く」ところに「幸福」はないと諭す母親は王子の本質に近い人生の知恵を持っているようです。
このような町の人々はカリカチュア的に描かれて作者の社会観や時代批判などを分け持ちつつ、また物語の最後にも出てきて、すっかり鉛の塊に過ぎなくなった王子像を撤去する役割を物語展開上では果たしながら、王子とつばめを価値付ける大枠の機能をも担ってゆきます。
2
続いて、王子に出会う前のつばめの物語が語られています。これは自然的な愛に対する挫折の単純な物語です。葦のすらっとした腰つきが気に入って、「君を好きになってもいいかい」とラブコールをしたのですが、彼女はうなずいたり、お辞儀をしたり、首を振ったりするばかりで、何も話してくれないのでした。葦のなのですから当然ですが、その自然的本性への理解と受容へと進むことなく、つばめは「でも、僕は旅をするのが好きなんだから、僕の妻たるものも、旅をするのが好きでなくっちゃ」と言い「僕と一緒に行ってくれないか」と要求を突きつけ、拒否されるや「僕のことをもてあそんでいたんだな」と叫んで飛び去りました。
若く幼い愛です。この段階の愛は自分に相応しい存在を見つけようとする、相手の中に自分にとっての価値の有無を問う愛です。自己追求と自己達成の手段または道具として都合のよい存在を求める、獲得欲に過ぎない愛です。まさにそれは自身の自然的性質を一歩も出ることの出来なかった葦と同様に、自分の枠を出ることのない自然的な欲求に過ぎないものです。ですからここにも出会いと求愛と別れがありますが、涙はありません。獲得の失敗があるだけで、本当の悲しみなどここにはないのです。でも自分は真剣で純粋だったと思うのです。だから「僕のことをもてあそんでいたんだな」と的外れな叫びをするのです。つばめはこの後、像として立てられた王子に会いますが、王子が人間として生きていたときの生も、このつばめと似て、自分の枠を出ることのない「サンスーシの宮殿(sans souci とは悲しみや憂いがないという意味で、「無憂宮」とも訳されます)」の内側のものであったのです。
自然的存在として生まれたものは、人もつばめも多かれ少なかれそのような段階を通り、必ず愛に挫折して(すべきなのです)、次の段階に、別の愛との出会いに進まなければなりません。
3
こうして、つばめは本性が指さす目的地であるピラミッドに向けて飛びたち、一日中飛んで、王子の町に着きました。つばめの休み場は町からはるかに高い柱の上の王子の像の足の間でした。「新鮮な空気のある場所」他の訳では「さわやかな風のかよういい場所」と書かれています。いずれにせよつばめは“fine position”を発見したのです。それは最初単なる一夜の宿りの場所としての“fine position”でしたが、やがて王子と出会うことによって、まさに人生の学びの“fine position”を与えられたと言っても良いでしょう。それは宿にあるまじき水滴から始まりました。三つの水滴が落ちてきたとき、つばめは遂に「上を見上げました。」つばめは、初めて上を見上げたのです。そこには自分の自然的性質よりも上にある存在との出会いが備えられていました。
幸福の王子の両眼は涙でいっぱいになっていました。そしてその涙は王子の黄金の頬を流れていたのです。王子の顔は月光の中でとても美しく、小さなツバメはかわいそうな気持ちでいっぱいになりました。
これがつばめの、ここから始まる物語の原体験です。そして、その涙である水滴にぐっしょり濡れながら「あなたはどなたですか」とつばめは問いました。既に一瞬にして心を打たれつつ「あなたはどなたですか」と問う者は、人生を変えるものに出会うのです。これは原理です。モーセもパウロもみな同じです。そして、それは彼が今まで体験的には知らないものであった〈涙する心〉でした。そして問う者には答えが与えられます。
「私は幸福の王子だ」
これは出会いと問いへの解答であると同時に、更なる問いになります。幸福ならばなぜ泣くのか?幸福と涙は矛盾しないのか?幸福とは何なのか?既にその涙である水滴に浸された者、その月光の中での美しさと「かわいそうな気持ち」に満たされてしまうという圧倒的な経験をさせられた者、つばめは、この問い(勿論まだそのときにはその問いの全貌は開示されていないのですが)から逃げることはもう出来ないのです。この「かわいそうな気持ちでいっぱい」になるという経験、「かわいそうだた、惚れたってことよ」と漱石も漱石を引用しながら『氷点』の三浦綾子も書いていますが、「かわいそう」と美しさはしばしば手をつないで人を内側から強く捕らえるのです。王子の悲しみに対する倫理心情的共感でも、王子がしたいと願っていた社会使命的共感でもありません。もっと別のレベルで、王子はつばめにとって圧倒的な存在なのです。涙でバプテスマ(洗礼)を受けてしまうということ、がある意味では否応なく暴力的に起きたのです。
4
王子はつばめに自分の前史を語りました。
「まだ私が生きていて、人間の心を持っていたときのことだった」と像は答えました。「私は涙というものがどんなものかを知らなかった。というのは私はサンスーシの宮殿に住んでいて、そこには悲しみが入り込むことはなかったからだ。昼間は友人たちと庭園で遊び、夜になると大広間で先頭切ってダンスを踊ったのだ。庭園の周りにはとても高い塀がめぐらされていて、私は一度もその向こうに何があるのかを気にかけたことがなかった。周りには、非常に美しいものしかなかった。廷臣たちは私を幸福の王子と呼んだ。実際、幸福だったのだ、もしも快楽が幸福だというならば。私は幸福に生き、幸福に死んだ。死んでから、人々は私をこの高い場所に置いた。ここからは町のすべての醜悪なこと、すべての悲惨なことが見える。私の心臓は鉛でできているけれど、泣かずにはいられないのだ」
幸福を自己実現すること、人々が幸福と考える皮相な幸福を実現すること、それだけが彼の人生の目的、強いられた目的でした。高い塀で、外の不幸を見ることがないように、純粋培養された幸福、その故に偽りである超人工的な幸福。その別名は〈快楽〉でした。人の世で幸福とはしばしば〈快楽〉でしかないものです。どうせ人は己の快楽のため生きるのだという倫理学の快楽原則の手ごわさを持ち出さなくても、この世に生きる人はみんなそれを体験的に知っているのです。でも、王子は一旦死んで(死ぬときも幸福に死んだとは、いったいどんな死に方だったのでしょう?)そこから、彼は一挙にすべての覆いを剥がれて、何も見えなかった者から、見える者に、何もかも見えてしまう者にされたのです。上記の引用の「町のすべての醜悪なこと、すべての悲惨なこと」という訳には少し不満があります。「町」は実は“my city”なのです。ただの町ではなく、「私の町」なのです。王子でなくても良かったのに、生きていたときと同じ王子のままで彼はそこに立たされたのです。それは、その町に対しての責任とその自覚を負わされているということです。しかも、私は知らなかった、知ろうともしなかったという深い悔恨と共に与えられるものでした。見ることは、見えてしまうことは、良き心にはいつも受難です。愛の反対は憎しみではなく無関心であったと、自分は愛のない愚かな王子でしかなかったと、王子は痛感(まさに痛みと共に感じた)したのです。何だったのか、あの幸福は?彼は目の前の「私の町」の醜さと悲惨さに胸の奥を掻き毟られ、かつての愚かさと現在の無力さに懊悩するしかなかったのです。
生きていたとき、王子の周りにいた沢山の廷臣や友人たちは、王子の快楽の享受という自己実現を助けるだけの存在でした。それは他者ではなかったのです。他者のいない世界に責任などありません。けれど、こうして高いところに、見えてしまう場所に立たされたとき、王子は他者の存在する世界をはじめて経験したのです。他者がいなければ、責任を問われることはありません。責任を問われなかった生前の王子はアイドルではあっても本当には王子ではなかったのです。彼は初めて自分が王子であることを自覚して「私の町」と言ったのです。そして、その町の人々の幸福なしに自分の幸福などありえないことを知るのです。
無関心によって守られた幸福から痛む愛へ、王子は変わり始めたばかりでした。(つづく)
このブログを書いた人

- 三浦綾子読書会代表/三浦綾子記念文学館特別研究員
-
1962年岡山県生まれ。1992年から2006年3月まで福岡女学院短大および大学で日本の近代文学やキリスト教文学などを講義。2001年より九州各地で三浦綾子読書会を主宰、2011年秋より同代表。
2006年、家族とともに『氷点』の舞台旭川市神楽に移住し、三浦綾子文学館特別研究員となる。2007年、教授の椅子を捨て大学を退職して以来、研究と共に日本中を駆け回りながら三浦綾子の心を伝える講演、読書会活動を行なっている。
著書に『「氷点」解凍』(小学館)、『塩狩峠』の続編小説『雪柳』(私家版)、編著監修に『三浦綾子366のことば』『水野源三精選詩集』(いずれも日本基督教団出版局)がある。NHKラジオ深夜便明日への言葉、テレビライフラインなどに出演。
最新の記事
 おたより2022年10月6日(木)おたより 23 朗読CD「李(すもも)」のご感想
おたより2022年10月6日(木)おたより 23 朗読CD「李(すもも)」のご感想 おたより2022年8月2日(火)おたより 22 「李(すもも)」朗読会のご感想
おたより2022年8月2日(火)おたより 22 「李(すもも)」朗読会のご感想 おたより2022年5月16日(月)おたより21
おたより2022年5月16日(月)おたより21 榎本保郎2022年3月11日(金)おたより ⑳
榎本保郎2022年3月11日(金)おたより ⑳