芥川龍之介「蜘蛛の糸」を読んで

今日7月24日は芥川龍之介の命日です。1927(昭和2)年、35歳でした。三浦綾子さんが5歳の時ですから、30歳年上だったわけです。この日未明、キリスト伝である「続西方の人」を書き上げたあと、斎藤茂吉からもらっていた睡眠薬を飲んで服毒自殺しました。使われた薬については芥川の主治医だった下島勲の日記などから青酸カリによる服毒自殺説を主張する研究者もいます。今日は最もよく知られた童話である「蜘蛛の糸」について書いた論文(解説)を載せます。かなり前に書いて未発表のままだったものなので研究論文としては発表できないものですが、資料や議論の煩雑な部分をカットし少し読みやすくしました。ご興味のあるところだけお読みいただけると感謝です。作品は各種文庫本もありますし、インターネット検索すると「青空文庫」としても出てきますので、ただで読めます。昔、国語の時間に読まれた作品でしょうか。またご一読いただければと思います。
芥川龍之介「蜘蛛の糸」を読んで ― 祈りの詩学のために4 森下辰衛
目次
一 芥川における「蜘蛛の糸」の位置
二 犍陀多の「善い事」
三 落ちること
四 御釈迦様
一 芥川における「蜘蛛の糸」の位置
1芥川の二面性
大正五年夏、最後の作品『明暗』を執筆中であった夏目漱石は、文壇に登場しようとしていた若い弟子芥川龍之介に書簡を送っています。(注1)
あせつては不可せん。頭を悪くしては不可せん。根気づくでお出なさい。世の中は根気の前に頭を下げる事を知つてゐますが、火花の前には一瞬の記憶しか与へて呉れません。うんうん死ぬ迄押すのです。それ丈です。決して相手を拵らへてそれを押しちや不可せん。相手はいくらでも後から後からと出て来ます。さうして吾々を悩ませます。牛は超然として押して行くのです。何を押すかと聞くなら申します。人間を押すのです。文士を押すのではありません。
ここに、芥川の作家的生涯は、既にその本質において予見されていたとも言えるでしょう。
芥川は文学という芸術の「火花」を求め、「みづから神にした」(「或旧友へ送る手記」)く思い、まさに文士として、馬のごとく世の「文士を押」し、自らの中の「文士を押」していったのですが、しかし、この「人間を押す」という力の要る業、すなわち人間そのものへの問いは常に骨の火のごと燃えていたのであり、またそれを知るがゆえに師もこの言葉を弟子に遺したのです。しかし芥川にとって、人間というものをそのおぞましき深淵にまで掘り抜いたこの漱石という作家の呼び声は、イカロスのごとき人工の翼で上昇せんとする羽撃きを虚偽として射ち、次第に自分を深淵へと引き込もうとするもののように思われたかも知れません。しかし、人生の年末を次第に意識せざるをえなくなってくるとき、再生のための拠所を与えるのもこの問いだったのでしょう。
「蜘蛛の糸」はお伽話であり、また発表誌「赤い鳥」の理想主義の枠付けが始めからあったゆえに、童話としては完成度の高い作品であるものの、正宗白鳥が批判したように(注2)「極り切つた秩序」に安住した「仮寝の夢」に過ぎないのでしょうか。また更にこの論点を進めて佐藤泰正が言うごとく(注3)、童話として芸術品化する時に「言わば宗教的混沌ともいうべき背後の深淵を切り棄てさせた」ゆえに「倫理的な異和感」を与えるような作品となっているのでしょうか。
2「地獄変」の裏面としての「蜘蛛の糸」
「蜘蛛の糸」とほぼ同時期に書いた作品に「地獄変」があります。平安時代、本朝第一の絵師良秀が、権力者大殿に「地獄変」を描けと言われて、見たものしか描けないと答えたところ、大殿は牛車に若い女を乗せて燃やして見せるのですが、その女が良秀の愛娘でした。ところが驚愕と苦悶の良秀の表情は次第に喜悦に変化し、遂に良秀は凄まじい迫力の「地獄変」の絵図を完成させてゆくのでした。人間としての良秀自身の心は、娘を焼き殺す炎熱に相応する地獄の業火へ入りながら、「センチメンタル=ヒューマニズムの超克」(海老井英次・注4)を果たして圧倒的な芸術作品を遺してゆくのです。この作品で、地獄変製作中の良秀が「炎熱地獄」への呼び声を聴くという場面があります。
「なに、迎えに来たと?だから来い。奈落へ来い。奈落には――奈落には己の娘が待っている。」
これこそは芸術家にとっての創作における秘められた暗闘であったと見ることができるでしょう。そうして出来上がった、良秀自身の人生を凌駕して遥かに見事な「地獄変」の絵は、「蜘蛛の糸」においては最後の何ものにも頓着しない極楽の蓮の花に形象化されています。そしてその蓮池の下の、「地獄変」の絵の裏面、もう一つの「地獄変」、地獄に落ちている良秀の姿を「蜘蛛の糸」は描いたのだとも言えるでしょう。
二 犍陀多の「善い事」
1「善い事」とは何か
この犍陀多と云ふ男は、人を殺したり家に火をつけたり、いろいろ悪事を働いた大泥坊でございますが、それでもたつた一つ、善い事を致した覚えがございます。と申しますのは、或時この男が深い林の中を通りますと、小さな蜘蛛が一匹、路ばたを這つて行くのが見えました。そこで犍陀多は早速足を挙げて、踏み殺さうと致しましたが、「いや、いや、これも小さいながら、命のあるものに違ひない。その命を無暗にとると云ふ事は、いくら何でも可哀さうだ」と、かう急に思ひ返して、とうとうその蜘蛛を殺さずに助けてやつたからでございます。
「いろいろ悪事を働いた大泥坊」で今は地獄に落ちている犍陀多(カンダタ)が「たつた一つ、善い事」をしたのを御釈迦様が思い出したことによって、蜘蛛の糸が下ろされるのですが、後から登って来た他の者たちに向かって「こら、罪人ども。この蜘蛛の糸は己のものだぞ。お前たちは一体誰に尋いて、のぼつて来た。下りろ下りろ」と喚いた瞬間に、糸が切れるというのが中心的な物語の構成です。糸が与えられることは切れることと対応する重要な点ですが、その理由となる「善い事」については余り明瞭にされてはいないようです。石割透は(注5)「〈犍陀多〉の行為は、このように自己の何かを犠牲にして善行を施した、と言える積極的な行為ではなかった。この場合に何故〈御釈迦様〉が〈犍陀多〉だけに注目し、救おうとされたのかという明確な根拠、必然性の提示に欠ける」とし、戸松泉は(注6)「釈迦の「善い事」への判断もきわめて恣意的なものとして、語り手自身の判断とのきわどい一致を表明しているかのよう」だと考えています。これらの批判そのものは正しくて、理由をきちんと考えようとすると、分からなくなるのです。
確かに犍陀多の行為は踏み殺すという〈悪をやめた〉ということに過ぎないのであって、例えば『塩狩峠』のような、何かを犠牲にして他の幸福のために働くというような積極的な善事ではありません。しかし、この「善い事」のゆえに糸が与えられ、それを犍陀多は登り、結果はともかく、地獄の「罪人ども」のすべてがこの糸を通って救われる可能性はあったのです。それは不意の思いつきに過ぎないというにはあまりに大きな可能性を持つもので、個人的な救いと、全人的な救いのまさに〈糸口〉がそこには企図されているはずなのです。優れた文学というものは常に、個人的な救いへの探求の過程の様を描きながら、同時に全人的な救いの問題をも考えているものです。ですから、「ローマ書」5章18節に「一人の罪によってすべての人に有罪の判決が下されたように、一人の正しい行為によって、すべての人が義とされて命を得ることになったのです」とあるように、この糸の与奪はすぐれて宗教的な出来事であり、非常に重要な意味を持っているはずなのです。ここにこそ中心があるはずなのです。
ではもう一度問いましょう。この物語における「善い事」とは何でしょう。「善い事」とは、蜘蛛を殺さなかったことですが、原典とされるポール・ケーラスの『因果の小車』(注7)では次のように語られています。
犍陀多は黙然たりき、彼は残酷なる人なりしが故に、生来嘗て一小善事をも為さずと思惟したればなり、されど如来は知り給はざる所なし、この大賊の一生の行為を見給ふに、彼嘗て森の中を行けるとき地上に一つの蜘蛛の蠢々たるを見たりしも彼は『小虫何の害をもなさず之を踏み殺すも無残なり』と思惟したることありき。
犍陀多が蜘蛛を殺さなかった理由として「彼は『小虫何の害をもなさず之を踏み殺すも無残なり』と思惟し」とあり、判断の基準は「何の害をもなさず」であって、自己を中心とした利害関係に立っています。利害という客観的な体系によってこの世界は明瞭に価値判定しうるもので、わずかに「無残なり」という情動があるだけです。利害による判断によるのであれば、基本的には金銭を強奪する泥棒の論理と同じ地平にあります。特別な発見や変化はないのです。しかし芥川はこれを次のように書き直しています。
そこで犍陀多は早速足を挙げて、踏み殺さうと致しましたが、「いや、いや、これも小さいながら、命のあるものに違ひない。その命を無暗にとると云ふ事は、いくら何でも可哀さうだ」と、こう急に思ひ返して、とうとうその蜘蛛を殺さず助けてやつたからでございます。
殺さなかった理由は明らかに転換しています。自己を中心とした利害という根拠を取り去って、「命のあるもの」の発見、その価値の発見に取り替えているのです。しかし、この蜘蛛の命の価値などというものが、犍陀多の中で、どのようにして発想されたのでしょうか。小さい命に価値があるという発見は、食うことの論理、殺人や放火さえも辞さない生命のエゴイズムの論理からは出てこないものです。 犍陀多のなかに突然の転回が起きているのです。
2見ることの転回
「善」の価値の中心は行為そのものでなく(なぜなら犍陀多の行為は残虐行為をやめただけであって、積極的な善事とは言えません。もしこれが善の本体ならば、悪事を一度でも思い止まったすべての人は―たぶん全ての人がそうでしょう―救われるでしょう)、この命そのものの発見にあります。行為にではなく、命の発見にあるのです。
〈見ること〉はルネサンス以降、聴くことに代わって人間の最も主要な統制的な感覚となり、理性と共謀することで自ら能動的な機能主体であるかのように振る舞ってきました。しかし本来の受動性に立ち戻る時に、〈見ること〉は人を存在に出会わせます。そのときその存在は発見されるだけの大人しい存在であることから抜け出して、〈我あり〉を語りつつ、自らを差し出してくるのです。このような関係性のうちに連れ戻された人は、対象的な認識を出て、絶対的な認識、というより本質的な出会いに入るのです。認識する者が認識される存在のもとに忘我的に魅了され、強く震い動かされながら“共に在る”というあり方です。そうしてそのときに、人の精神はほんとうの働きを始めることになります。真の出会いとはそういうものです。これを例えばフランクルは「精神的無意識」(注8)の働きと言いました。
「地獄変」の絵師良秀は「私は総じて、見たものでなければ描けませぬ」と言いました。この創作方法が、娘を焼かれるという人間的な悲劇を導く要因となっていました。自ら地獄を体験しつつ、その地獄にいる自己をも冷酷に観て描かねばならなかったのです。限界のところまで来た能動的な視覚です。そこで必要なのは、落胆を知らない意志力と解析力であり、〈感じ易い〉自己は抹消されなければならなかったのです。見ることは感じることではなかったし、見ると同時に見られるような関係に入ってはならなかったのです。しかし犍陀多は蜘蛛の這う地面の低さまで目を降ろしました。蜘蛛を対象として見るのではなく、地べたで対話的に見ながら、見られるところまで自己を降ろしているのです。「これも小さいながら」と言う時、その存在と出会い、その存在との間で〈我-汝〉という関係が結ばれていっているのです。「これも小さいながら」には「俺も」が含意されているでしょう。「小さい」もの同士が出会っているのです。つまり、良秀と違って、犍陀多においては、この瞬間、見ることは把握することではなく、出会うことであり、見られることであり、負わされることだったのです。
3責任存在への転回
その時、犍陀多にはすでに回心の原型の体験が与えられたのです。
蜘蛛の命に出会う状況「深い林の中を通りますと」とは、歩行の途中であるという意味です。人生は常に過渡的なものです。人生の始まりと終わりを人は自分では明瞭に意識できません。いつの間にか歩いている自分に気づくのです。そこで、ある日ある瞬間に、取り立ててどうということのない時間の中に、その瞬間は訪れます。犍陀多の人生の時間は殺人や放火や強盗の連続する時間でした。我々の人生も似たりよったりでしょう。自己がこの世界で生きてゆくための闘争、自己肯定があり、神の否定があり(ときには求めがあり)、自己追求を続ける道行きです。この自己追求・自己達成の人生の時間、そのような世界が、ある瞬間に、存在と出会うことを通して、それまでの人生の平板な利害の論理性を超脱して、一挙に責任が問われる世界へと変質してしまうのです。犍陀多の思いの中に現われた「命のあるもの」は、まさにpassio(受動的にして情熱的)な〈見ること〉を通して訪れた真理であり、客観的理性的な意識の外から訪れたて来たものなのです。
こうして犍陀多は実存的倫理の場に入りました。そのとき〈殺さない〉ということもひとつの大いなる行為になりました。訪れた真理に問われて、意志され、殺すことが停止される時に、世界は転換するのです。あり得なかった救いの根拠が瞬時に据えられました。彼の通常の生活において自動化されていた殺生が停止すること、〈思い留まる〉ということは、非常に高貴な、奇跡的なことでした。この作品のテーマを誰もがエゴイズムと読むのですが、それは“命と出会い”の対義語だったのです。
『因果の小車』では「犍陀多は黙然たりき、彼は残酷なる人なりしが故に、生来嘗て一小善事をも為さずと思惟したればなり、されど如来は知り給はざる所なし」とされていて、「善い事」を犍陀多自身は知らないのですが、芥川は「それでもたつた一つ、善い事を致した覚えがございます」と書き直し、犍陀多自身に意識させています。犍陀多がこの「善い事」を覚えていなければならないのは、それが試みの中心だからです。責任存在として「善い事」を再び反復できるかどうかが試みられるには、体験が意識されていることが必要だったのです。
宮坂覺は(注9)「〈視られていること〉に気づか」ず「自らも罪人である認識が欠落していた」ゆえに「犍陀多の救済は中断された」と指摘しますが、罪人意識の欠如は責めうるとしても、御釈迦様の存在すら知らない犍陀多に「〈視られていること〉に気づか」なかった責任を問うのは酷ではないでしょうか。ある日林の中で蜘蛛に出会うのと同じように、あるとき理由も知らされず、目の前に何気なく下りてくる蜘蛛の糸。それは謎であって、信心の試みではなく、実存的な倫理問題の地平の開始です。原話では釈迦が自らを犍陀多に示して語りかけ、犍陀多は釈迦と契約をしていますから、釈迦に対して信仰の責任を持つゆえに、その信心の弱さが問題になりました。犍陀多の「信仰やゝ乱れ来り」「一念疑の心動きたれば恐怖の思ひ禁ずる能はず」、下から来る罪人たちに叫ぶのでした。しかし釈迦と犍陀多の間に相識関係のない「蜘蛛の糸」では犍陀多は信仰の対象なしに責任を持たされているように見えます。つまり超越的な存在を持たない現代人の〈自由〉と不条理に条件づけられた宗教・倫理的状況設定なのです。責任とは、価値や権威からの眼差しを前提としてはじめて可能であるのに、どこへ行くかも知らずに登る犍陀多に責任を問い、糸を切るのは残酷であるとも考えられます。しかし犍陀多の救いの糸口は、蜘蛛の糸が与えられたことそのものの中に、一度は体験された「識られざる神」のうちにあったのですから、責任もまた、それに対してあったはずなのです。糸が切れたとき、犍陀多は釈迦の存在さえ知ることなく落ちてゆくのですが、しかしその時にようやく犍陀多は、少なくとも可能的には、糸を切った者、自分を処罰する者の存在を知り、責任を問うた者、責任存在として己れを認め、声を掛けていたはずの「識られざる神」に気づき得ることとなるのです。
三 落ちること
1命の場所へ戻ること
犍陀多に人間の弱さ、その悲しさを見て去ってゆく御釈迦様は残酷な性質に見えます。あるいは御釈迦様でなく芥川が残酷なのだとも見えます。不可能なほどの難しい試みによって、一人の罪人を裁き、糸を切り、再び地獄に、いや地獄のさらに底に、底のない底(abgrund)にまで落としてしまうのですから。あるいは、全責任は犍陀多にあるのであって、多くの普通の読者が読むように、彼のエゴイズムの地獄的性質が犍陀多を地獄に引き戻したに過ぎないのでしょうか。そしていずれにせよ、この結末は否定的なものなのでしょうか。確かに犍陀多が喚いた言葉の中には、糸が断たれる理由が具体的につまっています。自分が罪人であることを忘れ、根拠もなく糸の所有権を主張して他を排除し、己れが救われるためには他者が救いを求める自由をも抑圧しようとする。そこには信仰の弱さではなく、近代個人主義のエゴイスムの暗部が抉り出されていると読めます。
糸が切れたことは、糸が与えられたことと対応するはずです。糸が与えられたのは、まず蜘蛛に命の価値を発見(体験)しえた犍陀多の目、地べたまで降りて低くなったその目に個人的かつ全人的救いの可能性があったからです。しかし犍陀多はこの度は、利害勘定のエゴイズムの視覚しか持ちえませんでした。そこでは林の中での蜘蛛と同じように「罪人ども」を価値ある命として観ることが出来るかどうかが試されたのです。それゆえ「蟻の行列のやうに、やはり上へ上へ一心によぢのぼつて来る」や語感的に蜘蛛の足の蠢きをイメージさせる「まつ暗な血の池の底から、うようよと這い上つて」といった語で、犍陀多が最初に蜘蛛(小さな命)と出会った状況を指示しているのです。犍陀多は「罪人ども」に蜘蛛と同じ命の犇めきを受け取り、その呻きを聴くべきであったのです。
その時〈視ること〉は蜘蛛との出会いの時の二つのPassio(受動/情熱)から進んで、糸が切れるかも知れないという利害判断を超えて、もうひとつのPassio(受難)をも受け入れる愛の顕現を準備することが可能だったのです。それは非常にキリスト的なものです。
だからここで全人的救いの可能性の糸は切れ、犍陀多は他の「罪人ども」と共に落ちるのです。そして彼が落ちてゆくのは「血の池の底へ」です。そこは命が「うようよ」している所です。命の場所へ戻って、犍陀多は再び命をその低さにおいて見ることを学ばなければならないからです。そして「血の池の底へ石のやうに沈」むと書かれるときには、さらにその命の底の根底のない根底までも深降することも意味されているようです。
2「杜子春」「白」
芥川の作品には上昇しようとしていた者が落ちる話がほかにもあります。「杜子春」で杜子春は自力本願的に修業をして仙人になろうとします。それによってこの娑婆苦、人間の関係の虚しさと偽りの世界からの脱却を希求したのですが、馬に変えられた母親の愛情の前に、無言戒(声を出すな)を破って「お母さん」と叫んだゆえに、一切は水泡に帰し、振り出しに戻って洛陽の都の門に佇んでいる自己を発見することになります。これは挫折ではありますが、発見でもあります。確かに「杜子春」の結末は一つの価値の発見であり、「人間に回帰せんとする芥川の決意」(海老井英次・注4に同じ)として積極的に解釈されうるものです。
それは確に懐しい、母親の声に違ひありません。杜子春は思はず、眼をあきました。さうして馬の一匹が、力なく地上に倒れた侭、悲しさうに彼の顔へ、ぢつと眼をやつてゐるを見ました。(略)杜子春は老人の戒めも忘れて、転ぶやうにその側へ走りよると、両手に半死の馬の頚を抱いて、はらはらと涙を落しながら、「お母さん」と一声を叫びました。…………
まず声がする。そして、見られる杜子春。見られていることを見る。彼は自己達成・自己救済の目的から来る「戒めも忘れ」、走り寄るように見るのです。すなわち、地獄に落ちた者が、見ることのpassio(受動)へと転回するときに救いは来るのです。〈主体としての私〉が見るのではなく、むしろ脱自した私が〈そこに〉住まうように、抱きしめられて一つになるように見るのです。そして戒めを突き破って私の中に不意に浮上してくる声の体験が起きるのです。主体としての自己達成を極限まで追求した「地獄変」の良秀とそこから受動的経験としての命との出会いへと転回した「蜘蛛の糸」の犍陀多。杜子春のなかにはその両方があるのです。
実は杜子春はこのとき「無言戒」と逆の試みも受けていたのでした。「もしお前が黙つてゐたら、おれは即座にお前の命を絶つてしまはうと思つてゐたのだ」と鉄冠子は後で言いました。〈切断〉のイメージの裁きと処罰が背後にあったのです。こうして「無言戒」の失敗、自己達成・自己救済の失敗がそのまま真の合格であったことが事後に明かされることになります。
「蜘蛛の糸」では失敗が合格とは言えないのですが、犍陀多と杜子春とがこのような〈見ること〉の質、発語の瞬間の急転、という相似形を取っているのに、犍陀多の落下を否定的にのみ読んでよいだろうかと思えるのです。確かに「杜子春」の母は「人間」的なものを肯定的にかつ鮮やかに啓示していますが、「蜘蛛の糸」の「罪人ども」も密かにではありながら〈命というもの〉を自ら表すのです。「杜子春」は、いわば合格する犍陀多を描くのであり、それは犍陀多自身が林の中で体験した〈見ることー見られること〉の徹底によってもたらされるのです。
試される者が落ちるのは童話「白」でも同じでした。犬の「白」は友だちの「黒」が犬殺しに捕まえられる所に出くわしますが、怖くて自分だけ逃げました。そしておそらくはその為に「白」は黒くなってしまい、飼い主から「白」と認めてもらえなくなりました。それが「白」の落下であり「白」の物語はそこから始まるのです。犍陀多が蜘蛛のごとき「罪人ども」の所に落ちたように、「白」はまず「黒」の低さにまで落ちなければならなかったのです。そして「黒」を体験するに至らねば「白」の回復の物語は始まらなかったのです。
落ちることは目が降りてゆくことです。「罪人ども」の犇めく地獄世界のその根底なき根底まで、蜘蛛の命に出会いえた視覚、それが再び試みられ鍛えられるために、その根底へ降りてゆくのです。そして、その視覚が可能となるさらなる根底の発見へと降りてゆくのです。しかしそんなことが果たして可能なのか?それはわからないことでした。小説「海のほとり」には「僕は何か僕自身もながらみ(*注:貝の一種)取りになりかねない気がした」とあり、「ながらみ取り」は「沖へ泳いで行っちゃ、何度も海の底へもぐる」仕事で「おまけに澪に流されたら、十中八九は助からない」ような危険を含んでいる業だと書かれています。それゆえに御釈迦様は悲しそうな(と語り手は語るが、それは悲しみでないことをむしろ証ししているでしょう)顔をするのです。そして、おそらくはこの御釈迦様の視力も、その底の底へと共に落ちてゆくのです。
また言わずもがな、命に出会い、打たれる視覚を持ちえずに落ちて行ったのは「地獄変」の良秀=そこまでの芸術家としての芥川自身であり、彼はこの深み、生命の蠢く所、その出会いのうちに、そして更に深く無意識のうちで神の声を聴くところにまで降りて行こうと意志しているのです。それゆえ実はこの落ちる重力はまさに恩寵でもあるのです。
四 御釈迦様
原典とは違って、「蜘蛛の糸」の御釈迦様は超越的な神的存在ではなく、退屈しのぎをするかなり勝手気ままな御釈迦様という人間臭い造形がされているとも読めるでしょう。原典では「如来は知り給はざる所なし」とあるように全知存在であり、地獄の罪人にまで自己を顕示し、自己に対する信心や離反によって救いあるいは裁く存在でしたが、「蜘蛛の糸」ではそうではありません。確かに犍陀多を見てはいますが、犍陀多が林の中で出会った蜘蛛や、中途の疲労や、下から続いて登ってくる罪人たちをすべて御釈迦様が準備して試しているとは感じられません。責任を問いうるとしたら、そうでなければならないのですが。
原典が見出されて以来、その比較において御釈迦様と犍陀多の間のコミュニケーションの欠如という指摘がされる(下沢勝井・注10)のですが、御釈迦様と犍陀多とがコミュニケートしないのには二つの理由があります。第一は先に書いたように宗教的質を原典のような仏教性ではなく現代の実存的倫理・宗教状況に転換したためであり、もう一つは御釈迦様と犍陀多は始めから関係があるからです。極楽は芸術の世界、地獄は現実の生、そして御釈迦様は架構された作家(書く人)としての自己でもあるのです。救いがたい人間のエゴイズムに「悲しさうな御顔」するような倫理的価値づけが作家のそれであるというようなことではなく、蓮の花の根元、芸術作品の深層部を自ら覗き眼鏡で覗きながら、作家は書くことの根底を探り直そうとしているのです。
或る日の事でございます。御釈迦様は極楽の蓮池のふちを、独りでぶらぶら御歩きになつていらつしやいました。
「ぶらぶら」歩くことは単なる恣意性を示すのでなく、むしろ内的には恣意的どころか最も意味の深い彷徨いがあり、飢渇があるのです。意図して歩く目的的行為ではないゆえに、自由な彷徨いであり、そしてそれゆえに意識されない世界で、更に本質的な問いの声に導かれているのです。彷徨うことと真理に呼び出されることとは根源的に連動し、彷徨う者はいつも〈ふち〉を歩くのです。別世界に接した、臨界の地帯を歩くのです。〈海のほとり〉を歩くのです。それが、書くことなのです。
しかし極楽の蓮池の蓮は、少しもそんな事には頓着致しません。その玉のやうな白い花は、御釈迦様の御足のまはりに、ゆらゆら萼を動かして、そのまん中にある金色の蘂からは、何とも云へない好い匂が、絶間なくあたりへ溢れて居ります。極楽ももう午に近くなつたのでございませう。
こう語り終えられる末尾に、芸術そのものへの否定は全くないように見えます。それは一切を超越して輝くものであらねばならないのです。しかし、その下には地獄があり、うようよとした命の悶えとひしめきがあるのです。そして、それらは別々のものでなく、下部があって上部があるのです。蓮には必ず根があるのです。
時刻も「午に近く」になりました。移ろう時間であるからには、やがては「午」を過ぎ、夕を迎えるはずであり、決して翳りのない永遠の時間でないことを語っています。それは極楽のふりをしている芥川自身の人生の時間でもあったのでしょう。
文士でなく人間を押すこと。芸術ではなく命を見出すこと。師に言われた勧めは、彼の命綱でもあり、良く良く分かっていたことでした。自意識の苦しい高みから地べたに降りて、もっと本当の存在に出会える場所、命に見られる経験を見出さなければと、彼の作家生涯の後半は人間としての自分自身や家族や土俗的なものや無意識の領域などへと〈降りて〉ゆこうとする道程でもありました。自分が命を見たのでは足りない、命に見られる、命に見出だされる経験でなければならない。その求めが、最後におそらくは断末魔のような苦しみのなかで、キリスト伝「西方の人」「続西方の人」を書かせたのかも知れません。
注(1)大正五年八月二十四日付、芥川龍之介および久米正雄宛書簡。
(2)正宗白鳥「芥川氏の文学を評す」「中央公論」昭2・10
(3)佐藤泰正「芥川龍之介の児童文学」「国文学」昭46・11
(4)海老井英次「芥川文学作品論事典」『芥川龍之介必携』昭54・2
(5)石割透「蜘蛛の糸」(「芥川龍之介」第3号)平6・2
(6)戸松泉「『蜘蛛の糸』の語り手」(「芥川龍之介」)平6・2
(7)ポール・ケーラス『因果の小車』鈴木大拙訳・明31年
(8)V・E・フランクル『識られざる神』みすず書房、昭37・3
(9)宮坂覺「〈視ること〉〈視られていること〉中断された救済」(「芥川龍之介」)平6・2
(10)下沢勝井「蜘蛛の糸」(駒尺喜美編著『芥川龍之介作品研究』八木書店、昭44・5)
このブログを書いた人

- 三浦綾子読書会代表/三浦綾子記念文学館特別研究員
-
1962年岡山県生まれ。1992年から2006年3月まで福岡女学院短大および大学で日本の近代文学やキリスト教文学などを講義。2001年より九州各地で三浦綾子読書会を主宰、2011年秋より同代表。
2006年、家族とともに『氷点』の舞台旭川市神楽に移住し、三浦綾子文学館特別研究員となる。2007年、教授の椅子を捨て大学を退職して以来、研究と共に日本中を駆け回りながら三浦綾子の心を伝える講演、読書会活動を行なっている。
著書に『「氷点」解凍』(小学館)、『塩狩峠』の続編小説『雪柳』(私家版)、編著監修に『三浦綾子366のことば』『水野源三精選詩集』(いずれも日本基督教団出版局)がある。NHKラジオ深夜便明日への言葉、テレビライフラインなどに出演。
最新の記事
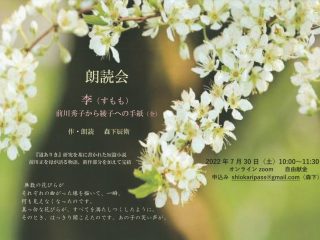 おたより2022年10月6日(木)おたより 23 朗読CD「李(すもも)」のご感想
おたより2022年10月6日(木)おたより 23 朗読CD「李(すもも)」のご感想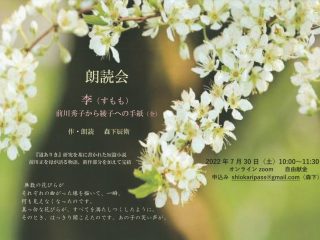 おたより2022年8月2日(火)おたより 22 「李(すもも)」朗読会のご感想
おたより2022年8月2日(火)おたより 22 「李(すもも)」朗読会のご感想 おたより2022年5月16日(月)おたより21
おたより2022年5月16日(月)おたより21 おたより2022年3月11日(金)おたより ⑳
おたより2022年3月11日(金)おたより ⑳
