洞爺丸遭難事件と『氷点』

書き直し
『氷点』の懸賞小説入選が決まって間もなく、朝日新聞から新聞小説の一日分三枚半を三枚強に書き直してほしいとの要請がきたとき、光世さんが、書き直すなら1954年に起きた洞爺丸遭難事件のことを入れてはどうかと提案して、二人は函館まで出向いて行って調べることにしました。エッセイ集『それでも明日は来る』にある「青函連絡船の思い出」という文章を見ますと、『氷点』連載が始まって半年ほどたった昭和40年5月の連休の頃、三浦夫妻は函館に行き、洞爺丸の生存者の一人函館教育大学の美術の教授渕上巍氏を紹介されて、体験談を聴きました。ゼミの若い学生幾人かを連れて本州にスケッチ旅行に向かう途次、遭難し、一行のうち生き残ったのは教授一人、学生は誰も助かりませんでした。綾子さんはこの教授の体験をつぶさに尋ねて『氷点』の啓造の体験の中に書きました。渕上教授には、若い学生に死なれ自分ひとり生き残った者の苦悩と悲哀が滲み出ていました。その後時々教授は思い出したように葉書を下さったのですが、後には「カトリックの洗礼を受けた」という葉書もありました。
宣教師
洞爺丸には三人の外国人宣教師が乗り合わせていました。カナダ出身のストーン宣教師、アメリカから来たリーパー宣教師、カナダ合同教会のオース宣教師です。オース宣教師は奇跡的に助かりましたが、ストーン、リーパー両宣教師は七重浜で遺体が発見されました。
事件後、日本経済新聞は、二人の宣教師を、救命具をゆずり、乗客を励ましながら死んでいった「北海に散った外人宣教師」として報じました。『氷点』を書いた段階では、綾子さんはこの二人の宣教師のことをつぶさには知らず、名前や年齢などを知ったのは後年であったようです。
亡くなった一人、アルフレッド・ラッセル・ストーン宣教師は、1902年、カナダのオンタリオ州ハイゲート村にアイルランド系農民の子として生まれ、幼い頃から農業を愛しました。トロント大学などで学んだ後、牧師となり、1926年9月来日。東京で日本語を学んだ後、1928(昭和3)年に長野に赴任、メソジスト派の教会を基盤に、各地で農民福音学校を開催、隣保館を作り、保育園を開設しました。ストーン宣教師は西欧の珍しい野菜を移入して野尻湖周辺での栽培を推進し特産品にするなどしたので、、野尻湖のほとりには村人によってストーン牧師の記念碑が建てられています。ストーン宣教師が信州農民福音学校の参加者に贈った聖書には、「土を愛し、人を愛し、神を愛せよ」と書かれていました。彼は日本人と同じ生活をしようと、日本食を食べ、日本の民家を愛し、囲炉裏を囲んで集会をしては、流暢な日本語で語りました。戦前は北信地区を中心に農村伝道、戦後はララ物資の配分に奔走し、生涯を日本の農村伝道に捧げた宣教師でした。
1954年北海道の特別開拓伝道の働きを担うために北海道に赴任。同年9月26日、上京の途次、青函連絡船の洞爺丸で台風に遭遇して52歳で天に召されることとなりました。この最期の年の7月12日には旭川六条教会で説教をしていますし、江別太のキリスト村に『愛の鬼才』の主人公西村久蔵を訪ねたりもしています。ストーン宣教師は9月25日札幌を発って函館に向かい、26日は朝、日本基督教団函館教会で「平和の道」と題して説教し、午後14時40分の定時発であれば乗れない筈の洞爺丸が何時間も遅れに遅れて出港したので、間に合って乗船してしまうことになったのでした。
ディーン・リーパー宣教師は1920年、アメリカのイリノイ州の農場を経営する父のもとに生まれました。敬虔なクリスチャンの両親のもとで育ったディーンは父のあとを継ぐべく、イリノイ州立大学農学部に入学しますが、学内のYMCA(キリスト教を信じる学生たちの集まり)に参加して、アジアから帰国した宣教師に感化を受け、アジアに宣教師として行きたい希望を抱くようになりました。やがて太平洋戦争が長期化し、彼も召集されますが「武器は持ちたくない」との彼の希望が認められ、日本を研究する任務に就きます。これがディーンと日本を結びあわせることになりました。
1945、日本が降伏すると、日本YMCAの指導者としてリーパー宣教師は日本へ出発しました。焼け野原の東京、食料や物資の極度の欠乏、防空壕に住む人々を目の当たりにし、強い衝撃を受けたリーパー宣教師は、YMCA再建に力を尽す一方、自ら日本人になろうと努力しました。欧米人は二等以上に乗るのが普通であったのに鉄道はいつも三等に乗車、銭湯に行っては日本人と背中を流しあいました。またリーパー宣教師はプロ級の手品師でもありましたので、多くの人々を楽しませ、たちまち人気者になってしまう。四年の働きを終えた彼はアメリカに帰り、休暇の大半を大学に通って、牧師の資格をとり、一年半後に再来日。北海道と東北地方のYMCAを巡回して、9月26日、函館から青函連絡船洞爺丸に乗り込んだのでした。
リーパー宣教師は恐怖におびえる乗客に、やさしく語りかけ、自慢の手品を披露、あざやかな手さばきに、子どもも大人も大喜び。一時船室に落ち着きがもどりますが、やがて船は大きく傾き、船室に水が流れこみます。リーパー宣教師は、たまたま同乗していたストーン宣教師、オース宣教師と力をあわせ、悲鳴の渦のなかで逃げまどう乗客に救命具を配り、着用に手間取る子どもや女性を助けました。ストーン宣教師は、救命具のない学生を見つけ「あなたの前途は長いから」といって救命具をゆずりました。リーパー宣教師は女性や子どもたちに救命具を着せてやり、最後まで励ましの言葉をかけ続けたと伝えられています。
ディーン・リーパー宣教師の長男スティーブンは、やがて広島で平和運動の働きに従事し、長女リンダは『氷点』に父親のエピソードが書かれたことに感謝し、三浦綾子さんを訪ね、綾子さんもその時のことをエッセイ集『泉への招待』所収の「ミス・リーパーの来訪」に書いています。
宣教師の姿が示す愛
『氷点』上巻の最後に書かれた洞爺丸遭難事件の宣教師の姿には、愛というものがはっきりと示されています。洞爺丸が台風に遭って船が大きく傾いてほぼ真横になり、海水が流れ込んだ場面。
ふいに近くで女の泣声がした。胃けいれんの女だった。
「ドーシマシタ?」
宣教師の声は落ちついていた。救命具のひもが切れたと女が泣いた。
「ソレハコマリマシタネ。ワタシノヲアゲマス」
宣教師は救命具をはずしながら、続けていった。
「アナタハ、ワタシヨリワカイ。ニッポンハワカイヒトガ、ツクリアゲルノデス」
愛は、駆け寄って「ドーシマシタ?」と聞くのです。泣くしかないような時に、そんな私に気づいて、かわいそうに思って、その理由を聞いてくれるのです。涙の理由を聞いてくれる人はなかなかいません。本当に優しいこころで「ドーシマシタ?」と言ってもらえたら、それだけで救われる人がどれくらいいるでしょう?
そして、宣教師は「ソレハコマリマシタネ。ワタシノヲアゲマス」と言っています。私だったら「わしが困っとるんやから、お前のをよこせ」と言います。これはエゴです。自分の事情ではなく、その人の事情を優先するのが愛です。自分のことなんか問題にしてないのです。本当に辛くて途方に暮れて、怯えて、泣くしかなくなっている人のところに来て、その問題を担おうとする心です。「ソレハコマリマシタネ。オキノドクニ。デハ、オイノリシテオキマスネ、サヨウナラ、オゲンキデ」と言いながら去って行く、私のような偽者クリスチャンとは違います。彼は、「ワタシノヲアゲマス」と言うのです。与えるのは救命具ですから、「私の命を上げます」という意味です。文字通り命がけの愛「人がその友のためにいのちを捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません」とある愛そのままです。
そして更に宣教師は「アナタハ、ワタシヨリワカイ。ニッポンハワカイヒトガ、ツクリアゲルノデス」と語りかけています。私たちに生きるべき方向と使命を与えて励まして下さるのです。アウシュヴィッツを生き延びたのは、頑健な人ではなく、心に生き延びて果たすべき使命と希望を持っていた人でした。人を本当に生かすものは何か?それをこの愛は知っているのです。
綾子さんはここで宣教師に救命具を渡された人物を、青年ではなく二十代の女性にしています。それは、この宣教師の愛が、堀田綾子が体験した前川正の愛、前川正を通して体験した愛であったからではないかと思うのです。自身の肺結核の容易ではない病状と残された時間の少なさを悟ったその時に、彼は「世に在る己の者を愛して極みまで之を愛し」なさいという使命を受け止め、そのように生きようとしました。ここに描かれた宣教師の言葉は、1948年12月27日、結核療養所白雲荘を訪れた前川正の心の言葉だったのです。
「どうしました?綾ちゃん」と、前川は綾子さんに問うたでしょう。「それは困りましたね。僕の持っているものは何でもあげましょう」と本気で言ったのです。私の文学も、信仰も、そして命も上げようと、彼は本気で考えたのです。そして、「僕が死んでもあなたはあなたの道を歩みなさい、あなたにはあなたの使命がある」と語ったのです。それは『道ありき』に記された遺書にもはっきりと見て取ることが出来ます。
受けついで生きる
(みんな生きていたかったのだ)
奇蹟的に助かった啓造は、そう思ったのでした。だから、自分は死んだ人々の命を引きついで生きているように思えました。生きて帰ることが、単なる幸運とはいえないような、もっと厳しい、重たい命を注ぎこまれたような思いでした。
汽車の中まで照り映えるような、紅葉と美しい水の大沼もすぎた。新しい命を得てながめる風景は、苦しいほどに美しかった。
(あの宣教師は助かったろうか?)
あの胃けいれんの女に、自分自身の救命具をやった宣教師のことを、啓造はベッドの上でも幾度も思い出したことだった。啓造には決してできないことをやったあの宣教師は生きていてほしかった。あの宣教師の生命を受けついで生きることは、啓造には不可能に思われた。あの宣教師がみつめて生きてきたものと、自分がみつめて生きてきたものとは、全くちがっているにちがいなかった。 (「台風」)
これは堀田綾子の思いでもあったでしょう。あの嵐の夜を生き延びた者と、死んでいった者がいた。戦争の時代と、戦後の結核病棟の時代、多くの若い人が死んでゆきました。前川正もその一人でした。前川正は洞爺丸台風の年1954年の春に13年の闘病の果てに死にました。13年の闘病の果てに死んだ者と、昭和34年、同じ13年の闘病の後、癒されて結婚した堀田綾子。生き残った者は、死んだ者の心と命を受けついで生きなければならないのだと、堀田綾子は思ったでしょう。綾子さんを愛するゆえに、早く治って医者になって彼女の療養費を出したい思いで、前川正は肋骨八本を切除するという危険な大手術を敢行しました。手術は結果的には失敗。彼は肋骨を遺して死にました。女はその骨を抱いて生きようと思いました。その骨の主のように、その骨の主の心を、女は生きようとしました。あの宣教師の命を受けついで生きることを心に問われ、考える啓造の思い、それは前川正に対する堀田綾子の思いでもあったのです。そして、前川を思い返し続ける堀田綾子と同じように、啓造もあの宣教師を幾度も幾度も繰り返し思い、一つの発見をしました。
(愛するとは……)
ふっと、洞爺丸で会った宣教師が思い出された。
(あれだ! あれだ! 自分の命を相手にやることだ)
啓造は思わず膝を打った。 (「雪虫」)
旭川に帰った啓造は、雪虫の飛ぶ晩秋のある日、その年の春に死んだ大学の後輩前川正のことを思いながら街をさまようように歩いて、遂に富貴堂書店の聖書の棚の前に辿り着き、口語訳聖書を手に取るのでした。
※写真上は津軽海峡を渡る青函連絡フェリーから見た青森側。下は大沼公園。

このブログを書いた人

- 三浦綾子読書会代表/三浦綾子記念文学館特別研究員
-
1962年岡山県生まれ。1992年から2006年3月まで福岡女学院短大および大学で日本の近代文学やキリスト教文学などを講義。2001年より九州各地で三浦綾子読書会を主宰、2011年秋より同代表。
2006年、家族とともに『氷点』の舞台旭川市神楽に移住し、三浦綾子文学館特別研究員となる。2007年、教授の椅子を捨て大学を退職して以来、研究と共に日本中を駆け回りながら三浦綾子の心を伝える講演、読書会活動を行なっている。
著書に『「氷点」解凍』(小学館)、『塩狩峠』の続編小説『雪柳』(私家版)、編著監修に『三浦綾子366のことば』『水野源三精選詩集』(いずれも日本基督教団出版局)がある。NHKラジオ深夜便明日への言葉、テレビライフラインなどに出演。
最新の記事
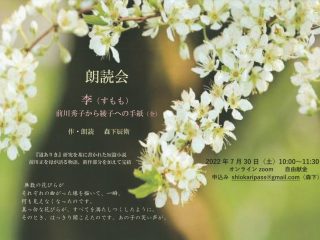 おたより2022年10月6日(木)おたより 23 朗読CD「李(すもも)」のご感想
おたより2022年10月6日(木)おたより 23 朗読CD「李(すもも)」のご感想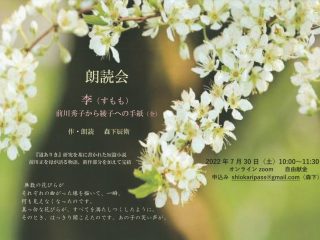 おたより2022年8月2日(火)おたより 22 「李(すもも)」朗読会のご感想
おたより2022年8月2日(火)おたより 22 「李(すもも)」朗読会のご感想 知里幸恵2022年5月16日(月)おたより21
知里幸恵2022年5月16日(月)おたより21 おたより2022年3月11日(金)おたより ⑳
おたより2022年3月11日(金)おたより ⑳
