広島の母、浦上の母 ― 平和の祈りへ

『銃口』の広島
『銃口』で、昭和20年8月21日、北森竜太と山田佐登志曹長は金俊明に助けられて下関へ帰還しました。その後、山田は広島に、竜太は旭川に帰って行きました。その竜太のもとに、しばらくして広島の山田から手紙が届きました。山田は原爆で跡形もなくなった家のあった場所に立って呆然としました。母は死んだと思いました。しかし「絶対この場にいたとは限らない。勝手に決めて絶望するのは止めろ」と言って励ましてくれる人がいて、ふと思いついて訪ねた呉の「泉屋」という旅館で母と再会しました。
ちょうど昼前だった。母は宿の前を竹箒で掃いていた。藁屑がたくさん落ちていた。モンペを穿いて、頭に日本手拭いをかぶって、母は何かを考えているふうに、ゆっくりと竹箒を動かしていた。私はすぐには声が出なかった。母は私に気がついて、竹箒を放り出し、駆け寄って、
「佐登志!」
と、私の胸にしがみついた。
「よう帰って来た! よう帰って来た! よう帰って来てくれた!」
うわごとのように同じ言葉を幾度も繰り返す母の肩を抱きしめて、(生きていてよかった。帰ることができてよかった)と、つくづく思った。銃を捨てたうしろめたさも、朝鮮人の服を着、闇船で逃がしてもらったことも、その時すっかり胸から消えた。子は母のもとに帰るべきだ、子は母のために生きるべきだ……そんな気持だったのかも知れない。(「明暗」)
母の待つ祖国を目指して、生きのびるために自ら銃を捨てる覚悟をした山田は、こうして母と再会しました。ここに、銃を自ら捨てた者への褒美、その困難な道を選んだ者への最高の祝福、母という命の懐かしさへの根源への帰還が描かれています。自分が殺されるかもしれないことを引き受けて、殺すことを決然として放棄した者に、それは与えられる命のふるさとであったのです。そして、待っていた母の祈りが裏にあったことは、三浦綾子がその再会の場所を、原爆の熱線とは逆に、「泉屋」と名づけたところにも感じ取られます。
原民喜
原民喜という作家がいます。彼は広島で被爆した経験から「夏の花」という優れた原爆小説を書きました。美しい文章で恐ろしいことが書かれてあるのですが、私がこの作品を読んで一番恐ろしいと思ったのは、ピカが来たとき「顔に受けた光線を遮ろうとして覆うた腕」を火傷した女性について書いてあるところでした。その女性はその時は火傷だけなのですが、後になってからその腕が「ひどく化膿し、蝿が群れて、とうとう蛆が湧くようになった。蛆はいくら消毒しても、後から後から湧いた。そして、彼女は一カ月あまりの後、死んで行った」とありました。消毒しても蛆が後から後から湧くという記述は象徴的で、外側だけでなく内側、人間というものの本質的な部分までも傷つける凶暴さがあり、その深さで傷つけられた人間の様が鋭く描かれているのです。「夏の花」という作品は、彼がこの世でただ一人心を開くことができた(彼は非常に内向的な性質でした)妻、その妻に先立たれたのですが、その妻の墓参りをするところから物語は始まります。そのとき彼が墓に手向けるのが黄色い夏の花。作品の題名になっています。そして数日後の8月6日に、その花は原爆の熱に焼かれることになるのです。深い悲しみと怒りを根底にしながら、静かで透明な文章ですべてが描かれていきます。
しかし、原民喜はそれから数年後、朝鮮戦争においてアメリカのトルーマン大統領が核兵器も使用すると公言したとき、怒りと悲しみと絶望の果てに吉祥寺-西荻窪間の国鉄線路に身を横たえ鉄道自殺しました。
浦上
長崎の浦上の天主堂には被爆したマリヤの像があります。
浦上は明治になって全村が政治によって離散させられた村です。政治が自国民を民族や宗教や政治思想のゆえに差別し隔離収容し、ある場合には虐殺することは、この百年ほどの間にも世界中で起こりましたが、ヒトラーの支配下のユダヤ人が体験し、スターリン時代にソ連で、あるいはポルポトの時代にカンボジアで人々が体験したことを、浦上の人たちはこの日本でしかも明治になってから体験しているのです。キリシタンの村人全部が捕らえられ、全国にバラバラに流罪になります、そしていろいろな拷問と多くの殉死と棄教。津和野の乙女峠などにも、その収容所跡が残っています。
この事件を「浦上四番崩れ」と言います。彼らはキリシタン禁令が解かれたのちに浦上に帰りました。そして1925年浦上の庄屋の屋敷(毎年正月に踏絵が行なわれた場所)のあった丘の上に、浦上天主堂が建てられました。そして20年後の1945年8月9日、聖堂は原爆で吹き飛ばされ、天使の像も焼け爛れ、マリヤは瓦礫の下になります。私は先年長崎に行った時にそのマリヤや天使の像を見ました。

この浦上の近くにカトリックの長崎純心女子中高があります。朝鮮戦争の時に、この純心女子中高生は、自主的に平和の祈りを始めました。毎朝の祈りは、半世紀以上たった今も続いています。朝鮮戦争当時の純心女子中高の生徒はトルーマンの言葉をどう聴いたでしょうか。親兄弟を原爆で殺された生徒も多くいたでしょう。親族や大事な友達を一人も失っていないような生徒はいなかったかも知れません。彼女たちの胸にも、怒りがあり、悲しみがあり、そして深い絶望が、本当に深い絶望があったと思います。彼女たちはこの状況に対する参加と抵抗を、怒りと力によってする可能性も、またある意味では権利もあったかも知れない。しかし、彼女たちの抵抗は怒りではなく、祈り、朝ごとの静かな祈りによるものでした。罪に対する時に、この世の悪の力に対する時に、力による抵抗ではなく、愛による抵抗、涙の祈りによる抵抗を行なうこと、この戦いの方法は神の涙を知っている者たちだけにできることだったと思います。※写真は上が被爆マリヤ像、下が被爆直後の浦上天主堂。
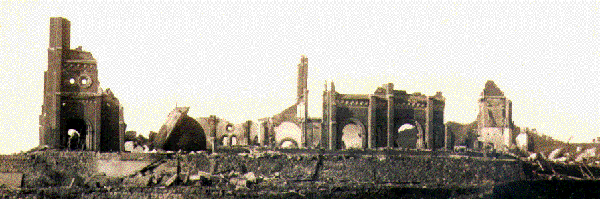
母の祈り
かけがえのない家族を殺された悲しみと怒りと恨みと絶望のなかで七転八倒するしかなかった彼女たちのその心の中に、一緒に悲しみ、泣き叫び、苦しみに転げ回り、そして慰めてくださるキリストの涙、そして母マリヤの痛みがあったのだと思います。少なくともそのような訪れを受けた娘、そのような信仰を持った娘がいたのです。泣いて下さるイエス、痛む母マリヤと共に、この世を悲しみ泣こうとした彼女はこうして祈る者になりました。そしてその一人の祈りの姿はそれを見たもう一人の娘に祈る勇気を与え、二人が祈る声はそれを見た第三の娘に希望を与え彼女を変えてゆきました。そしてやがて合唱するような平和の祈りが沸き上がってきたのだと思います。
彼女たちの中には最初、烈しい問いがあっただろうと思います。
「なぜ神はこんな悲劇を放置なさったのか?」
「神は無力ではないか?」
「そんな神に祈って何になるのか?」
しかし、キリストの涙と母マリヤの痛みを知った者はそれをもはや問わないのです。この悲しみと怒りとに七転八倒していた私の傍にキリストを見た者は、その父や母や兄弟や友達が、ただ苦しんで死んだのではなくて、キリストが彼らと一緒にいて、一緒に原爆の熱線に焼き殺されてくださったことをも知るからです。
被爆して壊れたマリヤの像の意味を彼女たちはよく知っている。彼女ら自身の痛みとして知っている。そこに神の愛を見る。そして彼女たちはそれを記憶し続けているのです。浦上の丘の下の学校で、75年経った今朝も祈り続ける、やがて母になって行くであろう彼女たち、私には彼女たちが、闘って傷ついて死んだ原民喜の母でもあるように思えるのです。そして彼女たちは山田佐登志の母でもあり、小さな小林セキさん(『母』の主人公)でもあると思います。命と平和の守りは彼女たちの涙の上にしかない。平和はいつも母の涙の上にしかない。綾子さんの心もそこに寄り添っているでしょう。

このブログを書いた人

- 三浦綾子読書会代表/三浦綾子記念文学館特別研究員
-
1962年岡山県生まれ。1992年から2006年3月まで福岡女学院短大および大学で日本の近代文学やキリスト教文学などを講義。2001年より九州各地で三浦綾子読書会を主宰、2011年秋より同代表。
2006年、家族とともに『氷点』の舞台旭川市神楽に移住し、三浦綾子文学館特別研究員となる。2007年、教授の椅子を捨て大学を退職して以来、研究と共に日本中を駆け回りながら三浦綾子の心を伝える講演、読書会活動を行なっている。
著書に『「氷点」解凍』(小学館)、『塩狩峠』の続編小説『雪柳』(私家版)、編著監修に『三浦綾子366のことば』『水野源三精選詩集』(いずれも日本基督教団出版局)がある。NHKラジオ深夜便明日への言葉、テレビライフラインなどに出演。
最新の記事
 おたより2022年10月6日(木)おたより 23 朗読CD「李(すもも)」のご感想
おたより2022年10月6日(木)おたより 23 朗読CD「李(すもも)」のご感想 おたより2022年8月2日(火)おたより 22 「李(すもも)」朗読会のご感想
おたより2022年8月2日(火)おたより 22 「李(すもも)」朗読会のご感想 おたより2022年5月16日(月)おたより21
おたより2022年5月16日(月)おたより21 おたより2022年3月11日(金)おたより ⑳
おたより2022年3月11日(金)おたより ⑳
