桜散る神楽岡公園を歩く
2020年5月12日の旭川市の神楽岡公園周辺の景色をお届けします。『草のうた』『この土の器をも』『銃口』「雨はあした晴れるだろう」などの三浦綾子作品の舞台になりました。桜散る神楽岡公園、三浦綾子文学散歩へようこそ。

忠別川対岸(右岸)から見た新緑の神楽岡公園。約41ヘクタールの広さがあります。公園ほぼ中央に崖があり、下の段は広く平らな明るい林と、大きな駐車場は忠別川河川敷につながります。夏季はキャンプやバーベキューをする人たちでにぎわいます。上の段は自然に近い林が広がり、森林浴散歩に適しています。北西の部分(写真では右奥)に上川神社があります。その向こうの公園外周に沿うプラタナス通りを挟んで神楽岡地区の住宅地が始まります。

右が神楽橋、左が新神楽橋。その下を忠別川が流れています。二つの橋が交わるように見える辺りの少し向こうに上川神社があります。『氷点』の物語は上川神社の夏祭りの午後から始まります。昭和8年の6月ごろ、綾子さんが通っていた大成小学校では、何年生以上かが三十日間上川神社に参拝したことがありました。毎日早朝境内に整列して柏手を打つのは気持ちよかったようですが、ある日参拝に向かう途中、橋を渡って坂を降りているとき、高等科の男子の自転車が突っ込んできて友人が二人けがをするという事件もありました。この神社参拝は綴り方教育に熱心な先生がいた大成小学校が当局からの嫌疑を晴らす目的で行ったのではないかと、綾子さんは推測しています(『草のうた』)。手前は宮前地区。

苔の上に散ったばかりの桜の花びら。白い花はニリンソウ。
 神楽岡公園の樹林。自転車に乗って夏にここを訪れた「雨はあした晴れるだろう」のサチコは「まったく神楽岡の木々は、したたるばかりに青かった」と日記に書いています。ハルニレ、ミズナラ、カツラなどの木々の間を散策できます。近藤多美子さんによる写真集『遥かなる 三浦綾子』には1990年10月、紅葉のこの林を歩く三浦夫妻の美しい写真が何枚も掲載されています。今は水芭蕉の花が終わり、若草が萌えて、木々も少しずつ芽吹いて緑が増えてくる季節です。
神楽岡公園の樹林。自転車に乗って夏にここを訪れた「雨はあした晴れるだろう」のサチコは「まったく神楽岡の木々は、したたるばかりに青かった」と日記に書いています。ハルニレ、ミズナラ、カツラなどの木々の間を散策できます。近藤多美子さんによる写真集『遥かなる 三浦綾子』には1990年10月、紅葉のこの林を歩く三浦夫妻の美しい写真が何枚も掲載されています。今は水芭蕉の花が終わり、若草が萌えて、木々も少しずつ芽吹いて緑が増えてくる季節です。

キャンプ場 。近隣の小学校は、この公園および川原で炊事遠足をします。カレーライスがほぼ定番です。『銃口』には「神楽岡」という章があり、六年生の竜太たちが炊事遠足に来たときのことが書かれています。ドッヂボールをしたあと、豚汁を作って食べながら、坂部先生は来月谷川冴子先生と結婚するのだと子どもたちに告白。みんな歓声をあげました。そのあと、上川神社を見て、「神さま」について子どもたちと自由に語り合ってから、坂部先生は「な、みんな、人はいろいろなものを拝んでいる。人間として何を拝むべきか、これは大変な問題だ。しかしな、人が信じているものをやめれとか、信じたくないものを無理に信じれとは、決して言ってはならんのだ」と教えてくれました。

公園の南東の端にある坂道。『銃口』では、北森質店の番頭の家が神楽岡公園の丘つづき(すぐ裏)にあり、ある日竜太と父親の政太郎は番頭の父親の見舞いに行って、逃亡した「朝鮮人のタコ」金俊明と出会います。政太郎に助けられた金俊明と竜太は北森家まで自転車で二人乗りして逃げますが、警察が検問しているかも知れない大きな通りでなく、もしかしたら一部はこんな道を走ったかも知れません。

公園内にある、緑の相談所。見えているのは、熱帯植物もある温室です。この周りの林では高い頻度でエゾリスを見かけることができます。

六花亭の趣のある看板と特徴的なプラタナスの幹。この道が“プラタナス通り”で、向こう側が神楽岡公園、右へ行くと旭川医科大学などがある緑が丘(『青い棘』の主要な舞台)、更に行くと旭川空港の方に通じています。

The Sun蔵人(くろうど)。三浦綾子記念文学館での案内人講座(11月~3月の月曜日で月2回、計10回開催)が14時半に終わると、ここの二階の喫茶スペースで有志によるお茶会をしています。和菓子系、洋菓子系、いろいろありますが、ロールケーキ“プラタナス”がここらしくて、美味しいです。

プラタナスの実。まだ葉が出ていません。

神楽岡の坂。この坂をしばらく登って途中から左側に入っていくと、前川家があります。正さんが亡くなった4年後の1958年、街中の9条17丁目からこの地に転居しました。結婚した翌月、三浦夫妻は結婚式で正さんの母秀子さんに祝辞をしていただいた御礼のために前川家を訪問しました(『この土の器をも』三章)

富良野線神楽岡駅。1959年6月21日の日曜日の午後、三浦夫妻は礼拝後、旭川駅でカレーライスを食べ、富良野線に一駅だけ乗り、ここで降りて、前川家を訪ねました。「わたしたち二人の突然の訪問を、彼の父も母も非常に喜んで迎えてくれた」と『この土の器をも』には書かれています。

このブログを書いた人

- 三浦綾子読書会代表/三浦綾子記念文学館特別研究員
-
1962年岡山県生まれ。1992年から2006年3月まで福岡女学院短大および大学で日本の近代文学やキリスト教文学などを講義。2001年より九州各地で三浦綾子読書会を主宰、2011年秋より同代表。
2006年、家族とともに『氷点』の舞台旭川市神楽に移住し、三浦綾子文学館特別研究員となる。2007年、教授の椅子を捨て大学を退職して以来、研究と共に日本中を駆け回りながら三浦綾子の心を伝える講演、読書会活動を行なっている。
著書に『「氷点」解凍』(小学館)、『塩狩峠』の続編小説『雪柳』(私家版)、編著監修に『三浦綾子366のことば』『水野源三精選詩集』(いずれも日本基督教団出版局)がある。NHKラジオ深夜便明日への言葉、テレビライフラインなどに出演。
最新の記事
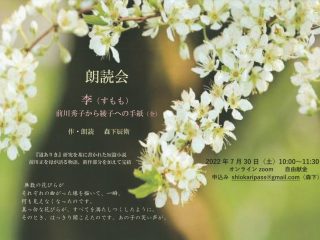 おたより2022年10月6日(木)おたより 23 朗読CD「李(すもも)」のご感想
おたより2022年10月6日(木)おたより 23 朗読CD「李(すもも)」のご感想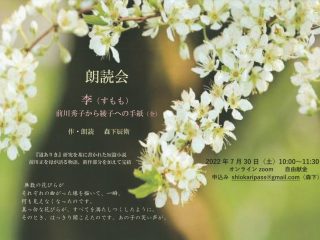 おたより2022年8月2日(火)おたより 22 「李(すもも)」朗読会のご感想
おたより2022年8月2日(火)おたより 22 「李(すもも)」朗読会のご感想 おたより2022年5月16日(月)おたより21
おたより2022年5月16日(月)おたより21 榎本保郎2022年3月11日(金)おたより ⑳
榎本保郎2022年3月11日(金)おたより ⑳
